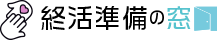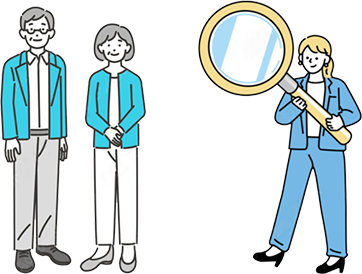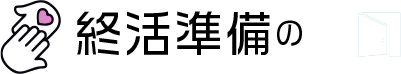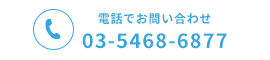今回は「準確定申告」のお話です。
被相続人が生前、自営業だったなどで確定申告を行っていた場合、亡くなった被相続人の代わりに行う必要があるものです。
言い換えれば、相続が発生したからといって必ず準確定申告が必要になる、というわけではありません。ただ、「しておいたほうがよい」というケースも存在します。また、準確定申告には通常の確定申告と共通する手続きが多いものの、なかには特有のルールもあるため、これらも確認しておきましょう。
「準」確定申告とは何か
本来、確定申告は所得があった本人が自ら行うものですが、亡くなってしまうとそれは不可能です。したがって、ほかの誰かが代わりに確定申告を行う必要が出てきます。これが「準確定申告」です。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得額について行うものですが、準確定申告は1月1日から亡くなった日までの所得額に対して申告します。
確定申告と準確定申告で異なる点
まずは確定申告と準確定申告で異なる点を挙げていきます。
所得の計算期間
前述したように、確定申告では毎年1月1日から12月31日までの所得額について、準確定申告では「1月1日から亡くなった日までの所得額」に対しての申告となります。
控除対象
確定申告では、所得の計算期間と同様に、12月末日の状態で配偶者控除や扶養控除が決定し、生命保険料や社会保険料は年間の合計支払額で控除ができます。
対して準確定申告では、「亡くなった日の状態で控除の有無が決定」し、生命保険料や社会保険料に関しては「亡くなった日までに支払いが済んでいる金額のみ」控除が可能となります。
申告期限
確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日が申告期間です。
対して準確定申告は、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」が期限となっています。
申告義務者
確定申告は所得があった本人が申告しますが、準確定申告の場合は本人が亡くなっているため、「相続人全員」が申告義務者となります。相続人全員が確定申告書に署名し、押印することが必要です。
申告先の税務署
確定申告では、申告者本人の住所地の管轄税務署が申告先となりますが、準確定申告では「故人が生前住んでいた住所地の管轄税務署」に申告します。申告者、つまり相続人の住所地ではないことがポイントです。
準確定申告が必要なケース
絶対にしなければならないケース
基本的に、故人が確定申告を必要としていた人だったのであれば、準確定申告をしなければなりません。たとえば、故人が以下のような人に当てはまった場合です。
・事業所得や不動産所得がある
・2,000万円を超える給与所得がある
・複数の勤め先からの給与所得がある
・給料の年末調整が行われていない
・給与所得・退職所得以外の副業で20万円を超える所得がある
・公的年金による収入が400万円を超える
・生命保険の満期金や一時金を受け取った
・土地や建物を売却した
・株式などを売却して源泉徴収されていない
など。
した方がよいケース
義務ではないがした方がよい、というケースもあります。還付金が受けられる場合が、これにあてはまります。
たとえば、
・年末調整が行われていない場合
・医療費控除を受けられる場合
・配偶者控除・扶養控除・寄付金控除を受ける場合
などが挙げられます。
準確定申告が不要なケース
簡単にいってしまうと、そもそも被相続人に通常の確定申告が必要なかった場合、準確定申告も不要です。たとえば、
・勤務先が1か所だけで、年末調整されている場合
・年金収入が400万円以下であり、その他の所得が20万円以下の場合
などです。
準確定申告の手続き
準確定申告であっても、基本的に確定申告で用意する書類や手続きの流れに違いはありませんが、注意点や追加の書類があるため、一通り順を追って見ていきましょう。
1.確定申告のための資料を探す
本人であれば申告のための資料がまとめてある場所を把握していますし、前年の資料を参照して申告書を作成することも可能ですが、第三者の場合そこまでは不可能です。したがって、確定申告をきちんと行えるように資料を探してそろえ、準備を整えなければなりません。
2.申告書を作成する
通常の確定申告と同じ要領で作成します。必要書類を国税庁のホームページからダウンロードして記入していきます。
ただし注意点としては、準確定申告の場合「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」という書類の提出が追加で必要になることです。こちらもダウンロードで入手できます。
さらに、準確定申告では相続人全員の連署が必要となります。または連署せず、それぞれの相続人が個別に提出します。これが「準確定申告は相続人全員で行わなければいけない」という意味です。
3.申告を行う
完成した申告書は、税務署窓口に持参または郵送での提出となります。また、電子申告の場合はe-Taxでの提出も可能です。
準確定申告に関する注意点
亡くなった日によっては2回必要になる
被相続人が1月から3月までの間で、前年度の確定申告を行う前に亡くなった場合は、前年分の所得についてと年が明けてから亡くなる日までの所得についてと、2回の準確定申告が必要になります。
この場合、申告の期限は準確定申告のものが優先されます。たとえば亡くなったのが2月20日であったとしたら、「前年度分」と「1月1日から2月20日までの分」の2種類の準確定申告書が必要になりますが、どちらも準確定申告の期限である「相続開始日の4か月以内」つまり6月20日までに提出します。前年分を亡くなった年の3月15日までに申告しなければならないわけではない、ということです。
電子申告も可能になった
以前は準確定申告については電子申告が不可能でしたが、令和2年度からは可能となりました。よって、e-Taxを利用しての申告もできるようになっています。
まとめ
準確定申告は、一部特有の手続きはあるものの、基本的に確定申告と同様の流れで進めることができるので、そこまで難しく考える必要はないでしょう。
しかし実は、1番の問題はそこではありません。もっとも考慮しなければいけないのは、「相続人が確定申告をしたことがない、まったく知識がない」という場合です。
相続人自身も確定申告が必要な人であれば、経験や知識もあるでしょうから、準確定申告ではポイントさえ押さえれば問題はないはずですが、そうでない場合は確定申告について一から勉強しなければいけない、ということになります。
準確定申告の期限は「相続の開始を知った日から4か月以内」です。相続人に確定申告の知識がないのであれば、とにかくできるだけ早くから着手しておくことをおすすめします。