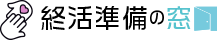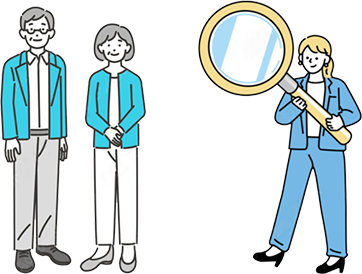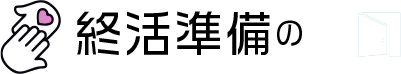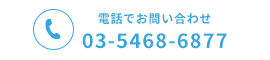自分や家族が余命宣告を受けたら、という想像をしてみたことはあるでしょうか。正直、誰もが自分には無縁のものとして考えているものではないでしょうか。
もし余命宣告を受けたら、一体まず何をすればいいのでしょうか。気が動転してしまって、まずは何も手につかないかもしれませんが、順番を追って先々のことを考えていければそれでいいのです。
今回は余命宣告を受けてから、終活としてどんなことをするべきか、というお話です。
余命宣告とは
余命宣告は、「あとどれくらい生きられるのか」という期間を医師から患者に伝えることです。末期がんなどにかかっていて、現時点で行える「標準治療」を施したにもかかわらず、病状があまりよい方向に向かっていない際などに行われます。
「余命」の予測は正確ではない
ひとつ、間違ってはいけないことは、余命宣告された「余命」はまったく確実なものではなく、あくまで可能性とおおまかな目安である、という点です。
同様の病気で似た病状だった患者が生存していた期間を集計し、そのなかの半数の患者が亡くなった期間である「生存期間中央値」という、これまでの医学的なデータに基づいて出した数値であるに過ぎないのです。したがって、宣告された時期より前に亡くなることもあれば、完治する可能性さえゼロではないのです。
たとえば余命宣告で「あと2年」といわれたとしても、その期間中に新しい治療法が見つかることもあり、それを施すことで病気が治る可能性ももちろんありますし、反対に2年経たずに亡くなることもあります。
先述したように、余命宣告はたとえばがんの場合「手術」「抗がん剤」「放射線治療」といった「標準治療」の範囲内で行われることが多く、まだ「自由診療」や「先進医療」を試してみるという選択肢も残っているのです。
経験豊富な医師の余命宣告であっても、確実なことはありません。人によって体質や病状の進行には大きく個人差があり、現時点でこれまでのデータと照らし合わせることができても、この先どうなるかは本当にわからないからです。
つまり余命宣告は、寿命の確定ではありません。ショックであり、不安になるのは当然ですが、絶望することはないのです。
余命宣告されたらしておきたい「終活」
まずは落ち着いて受け止める
余命宣告を受けたら、誰しもが多かれ少なかれショックを受けるはずです。先々のことを考えるのはもちろん大切ですが、まずは自分自身の気持ちに向き合うことが必要です。感情がこみあげてくるのならばその感情に一度身をまかせてしまい、落ち着くまでは無理に抑え込まなくてもいいのではないでしょうか。
ひどく落ち込んでしまったり、強い不安を感じてしまったりした場合は、主治医や専門のカウンセラーなどに相談するのもひとつの方法です。そうして少しずつ状況を受け入れ、徐々に現実を見つめられるようになり、これからのことを考えていけばよいでしょう。
難しいことでしょうし、すぐにとはいきませんが、事実を事実と受け入れ、残された時間で何をするか、今後をどう過ごすか、ということを考えるように気持ちを切り替えることで、最期まで実りある充実した生をまっとうできるはずです。
医療行為の方針を検討する
今後、どのような方向性で医療行為を続けていくかを、医師と相談して決めていきます。残された時間をどう過ごすか、自身の素直で率直な想いと向き合って考えることが必要になるでしょう。
完治を目指す
余命宣告されたからといって、治る見込みがないわけではない、と述べた通り、その後の治療や経過によっては完治する可能性ももちろんあります。がんであれば、標準治療だけでなく先進医療を選択したり、セカンドオピニオンを求めたりしてみるという方法があります。
その結果、余命宣告をされたにもかかわらず完治に向かう、という可能性ももちろんありますが、金銭的・身体的な負担は大きくなる恐れもあるでしょう。しかし、あきらめてしまわずにまだ方法があるのなら、選択する価値は大いにあるといえます。
緩和ケアに移行する
緩和ケアとは、症状を改善するのではなく、苦痛を少しでも軽くするための治療です。言い換えると、来たるべき死を受け入れ、残りの生を穏やかに過ごすための方法です。
ただ、前述したように余命宣告をされたからといって、もう治る見込みがまったくないわけではないため、緩和ケアを選択するのは重い覚悟が必要となります。家族や医師としっかり相談して、後悔のない決断をするべきといえるでしょう。
延命治療をする
余命宣告期間よりもあとに、たとえば「孫の結婚式がある」など、どうしても見届けておきたい、やっておきたいことがある場合に選択しうる方法です。
完治を目指すのではなく、あくまで少しでも生を長らえるための治療となるので、自由が利かない闘病生活になる可能性があります。また余命宣告の期間自体が確実なものではないため、延命治療も希望通りにいくとは限りません。金銭的・精神的・身体的にかなりの困難が伴うことも考えられるため、こちらも十分検討する必要があるでしょう。
親族や友人・知人に伝えるか考える
余命宣告されたという事実を、周囲の人に伝えるかどうかを考えます。無理に伝える必要もありませんし、知っておいてもらいたいと考えるのももちろん当然です。自分はどう思っているのか、これも自分の心に向き合って「この人には知っておいてほしい」という気持ちがあるなら、伝えておくべきでしょう。直接話すことにためらいがあるなら、手紙を書くという方法でもよいのです。
後悔の残らないように、どうしたいか考えたいものです。
生命保険の確認をする
次項の「相続の準備」のひとつともなる過程で、生命保険会社に保険内容を確認しておきます。生命保険には「リビングニーズ特約」というものがついていることもあり、これは生命保険金の一部金額もしくは全額を生前のうちに受け取れる、というものです。治療費に充てたり、家族に遺したり、生前の生活を充実させたり、どう使うかを選ぶことができる便利なものです。この特約がついているなら、利用しておくかどうかも検討するとよいでしょう。
相続の準備をする
死後、遺産となって相続が発生する財産の内容を調査し、整理します。財産目録を作成し、誰に何をどのくらい相続させるのか考えて、遺言書の作成までしておければ、相続人同士の余計なトラブルの防止にもなります。
また、治療やお葬式のためにまとまった費用が必要となることも考えて、生前のうちから用意しておくと安心です。
公共料金や各種サービス、税金などに未納分がないかどうかを確認しておくのもよいでしょう。遺族が行う「死後事務」の負担を、少しでも減らすことができます。
お葬式の生前準備をする
亡くなってからあわただしくお葬式の準備をするのは、遺族にとってかなりの負担となるはずです。葬儀社を選んだり、葬儀の形式(一般葬・家族葬・直葬など)の希望を出したり、プランの内容まで考えておくと、遺族としても最後のお別れの時間をゆっくりと過ごせるでしょう。埋葬方法も、お墓に入るだけでなく樹木葬や散骨を望む人が近年は多くなっているので、希望する方式があるならそれも家族に伝えておきましょう。
遺影にする写真を選んだり、お葬式に呼んでほしい人をリストアップしたりということも行っておくとよいですね。
臓器提供の意思表示をする
もし自分の死後、臓器提供をしたいという気持ちがあるなら、その意思表明をしておきます。免許証や保険証、マイナンバーカードの裏面に記す・インターネットで申請する・「臓器提供意思カード」を用意しておくなど、近年は意思表明もさまざまな方法でできるため、手間もかからないでしょう。
デジタルデータの整理と処分
インターネットでの会員サービスや電子メールの利用などをしている場合は、解約の手続きを進めておきましょう。また、自分のパソコンやスマホに残っているデジタルデータも、見られたくないものがあるなら整理して処分しておくとよいでしょう。
特に近年は、課金サービスも充実しています。解約しておかなければ、いつまでも料金が請求され続けてしまい、家族に迷惑がかかります。
エンディングノートを書く
ここまで述べてきたことも含めて、死後家族が困らないための情報や、家族へのメッセージなどをエンディングノートにまとめておくのもよいでしょう。法的拘束力は持たないため、エンディングノートに書く希望はあくまで希望であり、叶わない内容ももちろんあるかもしれませんが、自分の気持ちや心の整理として記録を残しておく意味でも非常に価値があります。
その他にも、備忘録としての日々のメモや、これまでの自分の生い立ちなどの記録も載せておくと、家族があとで見返したときに、故人となった人を偲ぶよいよすがとなるでしょう。
したいことをする
病状が許す限り、しておきたいことを思い切って実現させましょう。小さなことでもよいのです。今すぐに実行できないことなら、リストアップしておくだけでも楽しみになります。一日一日を大切に過ごすために、後悔や絶望に打ちひしがれて時間を送るのではなく、できる範囲でやりたいことをやっていきましょう。
家族ができること
余命宣告を受けた本人のみならず、その家族にとっても現実はつらいはずです。しかし、家族にしかできないこともあります。
本人の希望にできるだけ寄り添う
自分の家族が余命宣告を受けることは、自分自身が余命宣告を受けるよりも時にはつらいでしょう。しかし、やはり宣告を受けた本人がもっともショックを受けているということは、覚えておかなければなりません。
望みを失って何もしないのではなく、できるだけ本人が希望することを聞いて、寄り添うことが大事です。残された時間を一緒に、悔いのないように過ごすため、本人が望むことの手助けをしてあげましょう。
本人をしっかりと支える
人はひとりきりで考え込んでいると、悪い方向にばかり思考が行ってしまい、不安になりがちなものです。できるだけ余生を一緒に過ごす時間を長く取れれば、お互いの不安を抑えられるはずです。
もちろん、ひとりで考える時間も必要ですし、残りの時間の過ごし方に対する考え方は人それぞれではありますが、お互いを大切に思っている関係性であれば、お互いを励まし合い、そばにいて手を握っているだけでもかまいません。最期まで少しでも多くの時間を一緒に、元気に過ごせるのがよいのではないでしょうか。
本人の状態について正しく理解する
医師から提供される本人の病状や治療の内容などについて、しっかりと把握・理解し、正しい情報を本人に伝えるように努め、本人の不安を軽減する手助けもします。
自分自身のことにも気を配る
家族や周囲の人も、身体的・精神的な負担は大きくのしかかっているはずです。あまり無理を負わずに十分な休息を取り、自身のケアもしっかり行いましょう。
余命宣告された人に言うべきではない言葉とは
繰り返しになりますが、余命宣告をもっとも重く受け止めているのは本人です。周囲の人がかけることばは、本人の心にひとつひとつ強く影響します。ネガティブなことば、逆に根拠のないポジティブ過ぎることばは、避けるべきといえます。
具体的には、以下のようなことばがけです。
〇しても仕方がない原因の追及(「なぜ病気にかかったんだ」「がんの家系だから」など)
〇病気や症状についてのぶしつけな質問(「どんな病気なの」「今のステージは」など)
〇あきらめのことば(「もう治りそうにない」「あとは好きなことをしたら」など)
〇根拠のない理由づけ(「こうなるのも仕方がない運命だったんだ」「信仰心が足りないからだ」など)
〇軽率な励まし(「がんばってね」「まだまだ生きられるよ」など)
〇気持ちのこもらない哀れみのことば(「かわいそうに」「どうしてあなたが」など)
など。
ことばをかけた側に悪意や他意がなくても、本人の受け取り方をくれぐれもよく考えて、ことば選びは慎重に行わなければなりません。
※余命宣告を本人に告げない選択をするなら
患者本人の性格や病状によっては、医師の判断で余命宣告を本人ではなく家族だけに行うことがあります。
家族としても、大切な人の余命宣告を受けることには大きな精神的打撃があるでしょう。しかし、そんななかでも「本人に余命を伝えるかどうか」という決断はしなくてはなりません。
もし、余命を患者本人に伝えない選択をした場合は、家族だけで医療方針の決断や今後の過ごし方を考えることになります。また、本人が不安な思いを抱かないよう、より気遣いが必要となるでしょう。
本人が余命を知るべきか、知らないままでいるべきか。それを家族が決めることにもつらい気持ちがつきまとうでしょう。じっくり考えて、どのような形であれ、本人も家族も、後悔のない過ごし方ができる決断をしたいところです。
まとめ
人は、誰もがいつかは生の終わりを迎えます。それがいつなのかを知らないだけで、避けられないものには違いありません。
余命宣告をされると、それまであまり考えてこなかった「死」というものに対して、じっくり自分自身に向き合って考えることになるでしょう。後悔や恐怖もあるはずです。しかし、自分のことをまず最優先に考えられる唯一の期間になるかもしれません。
そして、余命宣告は絶対的なものではない、ということも覚えておかなければなりません。まだ絶望するには早いのです。
後悔しない時間を穏やかに送れるよう、準備していきたいですね。