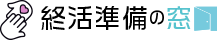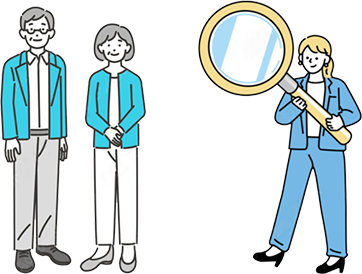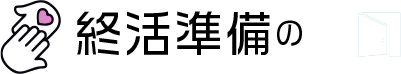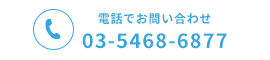遺産分割協議とは、相続財産があるときに「相続人の誰がどの財産を相続するか」という内容を、相続人全員で話し合うことです。
人生において、遺産分割協議を行う機会はそう何度もあることではないでしょう。したがって、わからないことだらけという方は多いはずです。
法律で決まっている法定相続人や遺言書との関係性はどうなっているのか、どのように話し合いを進めるのか、話し合いがうまく進まなかったらどうするのか、協議を終わらせる期限はあるのか。
今回は、遺産分割協議についてさまざまな観点から解説していきます。
遺産分割協議の概要
遺産分割協議とは
遺産を「誰が、どの財産を、どのくらいの割合で相続するか」ということを話し合うのが、「遺産分割協議」です。
財産の配分が遺言書によって指定されている場合は、その内容にしたがって分配し、また遺言書がない場合は、民法によって規定されている割合(法定相続分という)で分配する、ということが多いでしょう。
しかし、実は遺産分割協議において相続人全員の合意が得られれば、遺言書の内容や法定相続分とは異なる配分で遺産を分配することが可能となっているのです。
そのためには、協議には相続人全員が参加しなければならず、また行方不明の相続人がいる・認知症の相続人がいるといった場合にそれらの相続人を含めずに協議を行うと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
ただし、この場合の「全員が参加」というのは、全員が同時に1か所に集まって話し合いを行わなければならない、という意味ではありません。電話やメール、web会議ツールなどを使って話し合いを進めてもかまわないのです。
また、全員ではなく数人の協議によって決まった案に対して、協議に参加できなかった相続人から承諾を得る、という方法でも有効となります。
遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書」は、協議が完了したらその決定した内容をまとめた書類です。相続人全員が署名と押印をすることで、完成します。
遺産分割協議書は、基本的には作成すべきものだといえます。きちんとした書類で協議内容を残しておくことで、のちのちの相続人同士の予期せぬトラブルも防ぐことができるからです。
遺産分割の4つの方法
現物分割
相続財産を現物のまま分割します。現物分割が可能なもっともわかりやすい財産の例は、現金でしょう。ほかにも土地を分筆して分配するのも、現物分割です。
換価分割
相続財産の売却代金を各相続人に分割する方法です。不動産などの財産を売却し、得た代価を分け合います。
代償分割
本来の相続分以上の財産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。たとえば不動産に関する財産をすべて得た人が、その評価額分を分割して、各相続人に代償金を支払います。
例として、評価額1,000万円の土地を2人の相続人が相続する場合、片方が土地のすべてを取得し、もう片方の相続人に1,000万円の1/2にあたる500万円の金銭を支払う、ということになります。
共有分割
相続財産を処分せずに、複数の相続人でそのまま共有する方法です。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議の完了や協議書の完成には、特に法律上の期限はありません。しかし、10か月以内に相続税申告・納付という手続きがあるため、そこに間に合うように協議を進めていくべきといえます。
もしこの期間に遺産分割協議が終わらなければ、法定相続分による暫定的な相続税申告を行うことになります。協議がきちんと完了してから、修正申告などを行って、最終的な相続税の精算をします。
遺産分割協議をしなかった場合のリスク
一部の相続人による遺産使い込みの恐れがある
遺産を分割せず、そのままの状態で相続人全員の共有財産としていると、一部の相続人が遺産を勝手に使い込む、という恐れも考えられます。そうなると相続人間でトラブルや不信感が生まれるだけでなく、不当利得返還請求などの手続きも行う必要が出てきて、余計な手間がかかってしまいます。
遺産の活用がしづらい
遺産が共有状態にあるうちは、相続人の誰かが不動産を売却したいと思ったり、活用したいと考えたりしても、他の相続人が反対すると不可能となります。これも余計なトラブルを生んでしまう原因となるでしょう。
未来の遺産分割協議自体が難しくなる恐れがある
遺産分割を先延ばしにしていると、たとえば相続人の誰かひとりが認知症を発症してしまったり、相続人が亡くなってしまうことによって新たな相続が発生し、相続内容がややこしくなってしまったり、という事態も起こり得るでしょう。
今後何が起きるかはわからないため、遺産分割協議はできるうちに行ってしまうに越したことはないのです。
相続税の特例を受けられなくなる恐れがある
相続税には「小規模住宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった控除が用意されていますが、これらを利用するためには原則として相続税申告を期限内に行っている必要があります。
前述したように、遺産分割協議が完了しなければ相続税申告・納付が期限に間に合わないこともあります。せっかくの特例や控除を受けるためにも、遺産分割協議はお早めに。
遺産分割協議の手順
1.遺言書の有無と内容の調査
まずは被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があれば、原則としてその通りに遺産分割を行うからです。また前述した通り、相続人全員が合意すれば遺言書があってもその内容と異なる分け方にすることも可能です。
いずれにしても、遺産分割協議が完了してから遺言書が見つかった…ということのないように、この段階でしっかり遺言書の調査を行いましょう。
2.相続人の調査・確定
遺産分割協議には全員の合意が必要であるため、参加する相続人を調査・確定する必要があります。
相続人の調査のために、被相続人の死亡から出生までをたどって戸籍謄本を入手していきます。相続人が把握していなかった婚姻・離婚歴や養子縁組、非嫡出子の存在もあるかもしれないため、綿密に進めます。こちらもきちんと行っておかないと、協議が完了してから「他にも相続人がいた」という事態にもなりかねません。
3.財産内容の調査
相続人が確定したら、相続を行う財産の内容を調査します。どのような財産がどれくらいあるかを明確にしないと、そもそも分割ができません。
財産内容は、まず財産の種類(預貯金・不動産・有価証券・貴金属・借金・連帯保証債務など)を明らかにしましょう。プラスの資産もマイナスの資産もあわせて相続財産となるので、漏れなく調査し、可能であれば財産目録として一覧表を作成するとよりわかりやすくなります。
4.遺産の分配割合について話し合いを行う
「誰が」「どの財産を」「どれくらい」相続するかについて、相続人全員で話し合います。前述した通り、一か所に集まって話し合いを行う必要はなく、電話やメールで連絡を取り合ったり、数人で話し合った内容について協議に参加できなかった相続人から合意を得たり、という方法でも問題ありません。web会議ツールなどを使ってもよいでしょう。
5.遺産分割協議書を作成する
協議内容に全員の合意が得られたら。遺産分割協議書として書面を作成し、相続人全員が署名と押印を行います。協議書は相続人の人数分を用意して、各自が保管できるようにするとよいでしょう。
6.協議書の内容に沿って各相続財産の名義変更などを行う
遺産分割協議書を作成したら、遺産分割協議は終了…ではありません。実際に協議書の内容に沿って、各財産の分配・名義変更などを行ってようやく完了です。
不動産や預金口座などの名義変更には、遺産分割協議書と戸籍謄本なども必要になります。
遺産分割協議がまとまらなかったらどうする?
遺産分割協議は相続人全員が内容に合意しなければならないため、時として協議がまとまらないことももちろんあります。相続人同士で話し合いが平行線のままになってしまったら、どうすればよいのでしょうか。
遺産分割調停
調停委員という立場の人が仲介し、遺産分割の方法を話し合う場が設けられます。相続人同士という当事者だけの協議よりも、調停委員という第三者が入ることで、冷静な話し合いが期待されます。
調停内容で相続人全員の合意が得られれば、それに沿った遺産分割に落ち着きます。
遺産分割審判
遺産分割調停でも話し合いが決裂してしまった場合は、遺産分割審判という方法に進みます。こちらは家庭裁判所が法定相続分を基準にしながら、各相続人の言い分や主張もあわせて総合的に判断し、遺産分割の方法を決定します。この内容には、相続人全員が従わなければなりません。
遺産分割の際の注意点
遺産分割はやり直しできるのか
遺産分割協議が無効であるときは、やり直しが必須
遺産分割協議が何らかの理由で「無効」となった場合は、むしろやり直しが必須となります。
相続人全員の合意があれば、やり直しは可能
言い換えると、誰かひとりでもやり直しに反対すれば(その協議が前項のように無効でない限り)やり直しは不可能となります。
やり直しはやめておいた方がよい?
上記の通り、遺産分割協議は相続人全員の同意があればやり直すことはできますが、基本的にはやり直しはしない方がよいでしょう。
なぜかというと、やり直しによってすでに分配していた財産を移動する場合、相続ではなく贈与があったとみなされ、贈与税や譲渡所得税が課されるからです。これはすでに相続税を納付していても発生するので、二重課税ともなってしまう恐れがあるのです。
やり直すような事態にならないように、協議は慎重に行っておくのが賢明です。
音信不通・行方不明の相続人がいたらどうなるのか
相続人のなかに、行方が知れず、連絡も取れない人がいる場合、まるっきり無視して遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、行方不明から7年が経過していれば、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることで解決が可能となります。
また、7年以内であっても家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てて、行方不明の相続人に代わって協議に参加してもらうという方法を取ることができます。
とにかく、連絡が取れない相続人がいても無視してはいけません。その遺産分割協議は無効となり、やり直しをする手間がかかります。
認知症の相続人がいたらどうなるのか
認知症などで「判断能力が不十分」な法定相続人がいる場合、その相続人が参加した遺産分割協議は無効と判断される恐れがあります。
この場合は、家庭裁判所により選任される成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加することで解決できます。
まとめ
遺産相続には、どうしても「醜い」「泥沼になる」という悪いイメージがつきまといます。たしかに、協議が平行線で長引いてしまったり、相続人間でトラブルが起きたりという可能性は十分あり得ますが、そこには手続きやその過程の煩雑さが原因となっていることもあるでしょう。
まずは遺産分割はどのような手順で進めるのか、どんなことに注意しておけばいいか、ということをきちんと理解しておくことから始めましょう。それが相続をもっともスムーズに進めていける1番の早道だといえます。