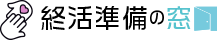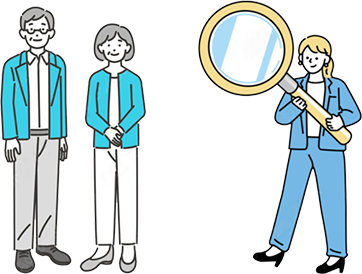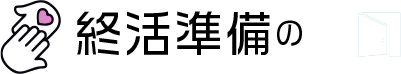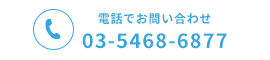そろそろ老齢の親の生活に心配が生じ始め、介護を考えているけれど、自分が帰省して介護するのも自分の元に親を呼び戻すのも、さまざまな事情でなかなか現実的ではない…そのような悩みを抱える人は、いまの時代とても多いものです。
そんななか、親にはいままで通りの環境でできるだけ自立した生活を送ってもらいながら、遠くにいつつもその支援をする「遠距離介護」という選択肢に注目が集まっています。
離れていても、親の生活をサポートする手段はたくさんあるものです。一昔前と違い、介護はひとりで抱え込むものではなく、地域が一体となって行うものとなってきたからです。
しっかり準備をしておけば、離れていても親の生活を見守ることはできるのです。
今回はこの「遠距離介護」について、成功させるポイントやメリット・デメリット、活用できるサービスを解説していきます。
遠距離介護とは
介護は、同居していたりすぐそばに住んでいたりできない事情があっても、さまざまな工夫や支援を駆使することで可能となるケースがあります。遠距離介護とは介護者と介護される側の住まいに距離がありながらも介護をする・されることです。
なぜ遠距離介護を選択する?
できれば親の元で介護をしたいと思っても、なかなか難しい事情はあるものです。
親世代からすると、介護を受けるために子世代のところに行くためには、住み慣れた環境を離れなければならず、それまで築いてきた人間関係やかかりつけの病院も手放すことになって、不安がつきまといます。子世代からすると、親世代の街に引っ越すには自分の仕事や子どもの教育環境、配偶者の生活にも配慮が必要となり、逆にそれがストレスになってしまいかねません。
遠距離介護であれば、どちらもその無理をする必要がなくなります。
核家族化が進み、子世代は都会で仕事を持ち、親世代は地元の田舎にそのまま住んで、それぞれ別の生活拠点を持つ家庭が増えている昨今、遠距離介護を選択する人も増加傾向にあります。お互いの身体的・精神的負担の軽減を考えると、それも当然といえるのかもしれません。
遠距離介護のメリット
お互いが住み慣れた環境から移らなくてよい
前述したように、細やかな介護をするためには、お互いが同居もしくはすぐ近くに住んでいることは理想かもしれませんが、元々の住まいが離れている場合、そうするためにはどちらかが転居しなければなりません。
少し前までは、子世代が自分の生活を後回しにして親世代の介護のために離職して親元に戻る、という事例も多く、子世代の人生も左右することでもあるため、大きな問題となっていました。
遠距離介護であれば、お互いが自分の生活環境に大きな変化を必要とせず、これまでの暮らし、子世代の仕事や育児に支障をきたすことなくそのまま継続することができるでしょう。
適度な距離感を保てる
これまでそれぞれの生活を送ってきた両者が、介護のために同居となると、いくら近しい関係であっても精神的にストレスを感じることもあるでしょう。やはり少し前には「介護うつ」も問題として取り上げられることも多かったものです。自分のそれまでの環境を変え、介護中心の生活になってしまうと、身体的にも精神的にも追い詰められてしまうことは、残念ながらあることなのです。
その点遠距離介護であれば、適度な距離が保てて自分の生活や時間を確保することができるため、時間にも余裕やゆとりが生まれ、「介護」という言葉による余計な力が入ることも少なくなるかもしれませんね。
介護保険サービスを利用しやすくなる
介護保険サービスのなかには、遠距離介護の場合だと制限なく受けられるサービスが存在します。たとえば、高齢者だけの世帯であれば日常生活の支援をしてくれる「生活援助」というものが挙げられます。
また、もし特別養護老人ホームに入所することになった際にも、遠距離介護の場合はその状況を考慮されて、入所の優先順位が高くなりやすいというメリットもあります。
遠距離介護のデメリット
緊急時の対応ができない
何かアクシデントが起きたとき、急な容体の変化があったときなどには、離れている分迅速な対応が難しいという点が、遠距離介護ではもっとも大きなデメリットでしょう。毎日すぐそばで様子を見ていられない分、日頃からこまめに連絡を取って状態を感じられるようにしておくことが必要です。
費用がかかる
遠距離介護では、月もしくは年に数回帰省することになりますが、その分交通費や宿泊費が必要になります。また、遠方と連絡を密に取ることが多くなるため、電話代などの通信費もかかるでしょう。
さらに、親だけで普段の生活を成り立たせてもらうためにも、手すりやスロープの取付など住宅改修費もある程度見込んでおかなければなりません(後述しますが、要介護認定を受けておけば住宅改修には助成金を受け取ることもできます)。
遠距離介護の準備とポイント
親の希望を聞いておく
どんな介護を受けたいのか、どこで生活をしたいのか、どこまで自力でやりたいかなど、不本意な介護生活を受けさせないためにも、まずは親に介護についての希望をひとつひとつ聞いておきましょう。
関係者全員がその希望を共有し、できるだけ希望に沿えるように動いていく指針になります。
要介護認定を受けてケアプランを立ててもらう
遠距離に限らず、介護が始まる際にはまず地域包括支援センターに要介護認定の申請をしましょう。認定を受けると介護保険サービスが受けられるようになるので、まず初めに最優先でやっておくべきといっても過言ではないことです。
介護保険サービスとは、費用の1~3割の自己負担で受けられる支援です。訪問型支援、通所型支援、介護用品や福祉用具のレンタルなどさまざまなサービスがあるため、必要なものを組み合わせて活用していけます。特に遠距離介護では助かるものが多くあるはずです。
無事に要介護認定を受けたら、ケアマネジャーを選定しましょう。介護保険サービスのプランニングをする役割を担ってくれる存在で、特に遠距離介護であれば介護者から連絡を密に取り、相談に乗ってもらうことになるので、コミュニケーションの相性がよく遠距離介護にも理解の深い担当者と巡り会いたいものです。
担当してくれるケアマネジャーが決まったら、ケアプラン(介護サービス計画)を立ててもらいます。どのように介護保険サービスを組み合わせて利用していくかというプランであり、ぴったりのプランを立ててもらうためにも状況や環境、事情などは事細かに伝えておくようにしましょう。
介護サービスの情報を集めておく
遠距離介護では緊急の事態に対応することが難しいため、いざというときに親の住まいの近隣にある介護サービスに頼ることもあるでしょう。また、容体の変化などで遠距離介護が難しくなったときには、改めて施設に入ることも考えられます。自分自身が離れていても信頼してまかせられるサービス・施設を早いうちから選べるよう、情報を集めておきましょう。
親の交友関係を知っておく
親が普段つきあっている友人や、仲のよいご近所さん、参加しているサークルなどを把握しておきましょう。遠方にいる自分の代わりに、いざというとき対応してくれる人を知っておくと安心です。
親の生活を知っておく
起床時間、就寝時間、外出状況や食事の内容、また趣味など、どんな生活を送っているのかも聞いて把握しておきましょう。いつ連絡が取れるのかがわかり、何に不自由しているかということにもすぐに気づく手助けにもなります。連絡が取れず異変を感じたときにも早急な対処につなげることができるでしょう。
親の経済状況を把握する
親の預貯金や保険、普段の収入・支出など細かいことも知っておきましょう。お金の話は親子といえどもなかなか切り出しにくいかもしれませんが、介護費用の予算を決めるうえでも必要なことです。万が一認知症になってしまうと、それからの確認は容易ではありません。元気なうちから把握しておくべきことです。
印鑑や通帳などの貴重品の管理場所も決めて、情報を共有しておくことも大事です。金銭についてきちんとしておくことは、家庭内や親族間のトラブル防止にもつながります。
介護の費用を見積もる
前述したように、介護認定を受けておけば介護保険サービスを受けることができます。これがないと、介護に必要な費用は全額自己負担となってしまうため、まずそちらの手続きが大前提です。
そのうえでケアマネジャーなどにも相談しながら、必要な介護サービスや福祉用具のレンタルを利用することも検討していくと、何にどのくらいの費用がかかるのか、見積もできるはずです。
住宅を改修する
上記とも重なりますが、介護認定を受けておけば住宅のバリアフリーリフォームのために助成金を20万円まで受け取ることができます。遠距離介護では、親世代がある程度自立した生活を送れることが前提であるため、そのサポートのために必要なリフォームは早めに行っておくことが大事です。
ICT機器や緊急通報システムの設置の検討
ICTとは「情報通信技術」のことです。最近は離れている家族の見守りのためのICT機器も多く登場しており、緊急ボタンを押すと警備会社が駆けつけてくれる緊急通報システムと並んで設置を検討するのもよいでしょう。自治体によっては無料で取付をしてくれるところもあります。
家族のなかで役割分担を決めておく
兄弟姉妹がいるのであれば、各人の生活などを考慮しながら役割分担をしておきましょう。誰かひとりに負担が集中しないよう、分散させながらも協力しあえる体制をととのえておくとよいですね。
もし時間的な問題があって役割を担えない人がいる場合には、資金援助を積極的に行ってもらうという方法もあります。
職場に相談しておく
子世代は転居する必要がないといえども、不測の事態で仕事を休むことも考えられます。あらかじめ職場には遠距離介護を行うことを報告しておき、上司や同僚の理解を得ておくことも重要です。介護休暇については職場の制度上どういう扱いになっているかということも、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
地域の高齢者サポートの仕組みを確認しておく
介護保険サービスを利用していないときは、地域包括支援センター(健師・社会福祉士・ケアマネジャーが配置されている、チーム単位での支援や相談ができる機関)や民生委員といった地域の高齢者サポートの仕組みを確認し、相談しておくとよいでしょう。
遠距離介護で利用したいその他サービス
配食サービス
栄養が考えられた食事を届けてくれるサービスです。毎日手の込んだ調理はなかなか難しいものですが、配食サービスがあれば食事面からの健康も維持することができるでしょう。自治体が民間業者に委託していることが多いため、まずは自治体にサービスについて確認してみましょう。
介護支援サービス
地域包括支援センターには、体操教室や認知症予防教室などさまざまな講座の開催情報が集まっています。こういったものも積極的に利用して、心身ともに健康に過ごせるよう、親に情報を伝えていくとよいでしょう。
交通費割引サービス
航空会社では、介護割引のサービスを用意している会社もあり、事前に必要書類をそろえて申し込んでおくことで利用できます。飛行機での帰省が多くなる場合には、ぜひ活用して少しでも交通費を節約したいですね。
遠距離介護をうまく運ぶポイント
コミュニケーションはこまめに
被介護者である親に対してはもちろん、ケアマネジャーや親の近くに住む人・友人、またかかりつけ医などとも、普段からできるだけこまめにコミュニケーションを取っていきましょう。異変にすぐ気づくこともできますし、それに対する早急な対応も可能になります。
いまは電話で音声のみの会話だけではなく、映像を通して顔や表情を見ながら話をすることもできる便利な時代です。また、スマホやパソコンの使い方を覚えてもらえることによってその他のさまざまな連絡ツールを活用することもできるでしょう。
手軽に、気軽に、コミュニケーションは可能な限り密に取っておくに越したことはありません。
常に情報収集を怠らない
地域でどんなサービスが受けられるか、高齢者向けの講座やサークルはどんなものが開講されているかなど、最新の情報は常に収集しておきましょう。親本人が行えればよいですが、なかなかすみずみまでは行き届かないものです。親がどんなことに興味があるか、いま何が必要かという希望を聞きながら、豊かな暮らしが送れるよう情報収集を欠かさないようにしましょう。
介護費用はできるだけ親の資産で
親の介護費用を、親の資産からまかなうことは、何も悪いことではありません。むしろ親の資産内で予算を組むことが大事です。子世代である兄弟姉妹の間で負担分が生まれてしまうと、その割合でトラブルを引き起こす原因にもなりかねないからです。
子世代には子世代の生活や人生設計があります。親の介護のために子世代の財産が侵食されるのは、本末転倒です。介護が始まる前に財産状況については親と十分に話し合い、無理のない範囲で介護予算を組むことが必要といえるでしょう。
余裕をもって施設入所も視野に入れる
遠距離介護は、緊急時に即座に駆けつけることが難しいというデメリットがあります。したがって、親の健康状態や認知症の度合いなどには常に気を配り、遠距離介護でできることに限界を感じる前に、介護施設入所も検討していくことが大事です。ひとりで何もかも抱え込んでしまう前に、ケアマネジャーに相談するなど、早めの行動を心がけましょう。
介護施設にはさまざまな種類があり、違いがよくわからないという方も多いかもしれませんね。介護施設には大きく分けて「公的施設」と「民間施設」の2種類があり、介護度や費用の程度、認知症の有無などによってさまざまなタイプに分けられています。
ここではそれぞれについて、簡単に解説しておきます。
介護施設の種類(公的施設)
行政機関が管轄していて、利用料が民間施設よりも安めという点が最大のメリットです。また介護度が重い人・低所得層・在宅介護が困難な人が優先的に入所できるという傾向もあります。
◯ケアハウス
比較的介護度の低い人向けです。費用もほかの施設より軽費であり、家事などの生活支援サービスが提供される「一般型」と、それにプラスして介護サービスも利用可能な「介護型」があります。
◯特別養護老人ホーム
通称である「特養」という言葉で聞いたことがある方は多いでしょう。基本的には「要介護3以上」の認定を受けている方が対象ですが、1~2の方も事情によっては特別入所が認められることがあります。
介護保険によって低価格で入所できること、看取りまでの対応も可能であることから、非常に人気が高く、入居待ちの待機者が多いところが難点です。
◯介護老人保健施設
通称「老健」です。病院に入院していて、退院後リハビリが必要な高齢者の在宅復帰を目指すことに特化した施設です。そのため、入所期間は短いという特徴があります。
◯介護医療院(介護療養型医療施設)
2018年4月に創設されたばかりの新しい施設です。医師の配置や医療設備が充実しているため、医療ケアが必要な高齢者に特化しているといえます。医師・看護師・薬剤師・栄養士が配置され、看取りにも対応、長期入居が可能な施設となっています。
介護施設の種類(民間施設)
民間業者が運営する介護施設は、費用やサービス内容が事業者ごとに大きく異なり、優先したいことや希望によって自分に合わせた施設を選べる点がメリットです。ニーズや経済状況を踏まえて検討できます。
◯介護付き有料老人ホーム
広い範囲の介護サービスが受けられる施設です。一番の特徴は「介護保険サービスが定額」である点で、高い介護度の入居者でも充実した内容の介護サービスを、費用を抑えて受けることが可能となっています。必要に応じて生活介助、生活支援、本格的な介護、看護、リハビリなどもサポートしてもらえます。
◯住宅型有料老人ホーム
介護度が高い人から自立した人まで、幅広い入居者がいる施設です。一番の特徴はイベントやレクリエーションが充実していて、ほかの入居者とともに楽しく生活することに重きを置いている点でしょう。
前項の「介護付き有料老人ホーム」では施設が定めた介護サービスを受けることになりますが、住宅型有料老人ホームの場合は在宅介護サービスも組み合わせることができるため、より自分に適した介護サービスを受けられるというメリットもあります。
◯サービス付き高齢者向け住宅
通称「サ高住」です。介護施設ではなく、「住宅」として扱われるもので、外出や外泊も比較的自由度が高く、介護サービスを受けながらもまさに「自分の住まい」のようにのんびりと暮らせるというメリットがあります。
◯グループホーム
認知症の方が少人数でグループとなり、サポートを受けながら共同生活をする施設です。各自ができること・できないことを踏まえて家事の役割を分担しながら生活し、認知症の進行をゆるやかにしながら、目の行き届いたサポートを受けられるという特徴があります。
まとめ
遠距離介護は「すぐそばにいられないから不安が大きい」というネガティブなイメージがあったかもしれませんが、さまざまな工夫を凝らし、また支援やサービスを活用することで十分成り立たせられるということがわかりましたね。
一昔前は介護というと、孤独で心身の負担が大きいものと思われがちでしたが、今はひとりで抱え込まなくてもさまざまなサポートが受けられます。親にも安心して穏やかな老後を過ごしてもらえるよう、遠距離介護のメリットを活かしてお互いに充実した生活を送りながら見守りたいですね。