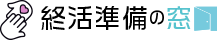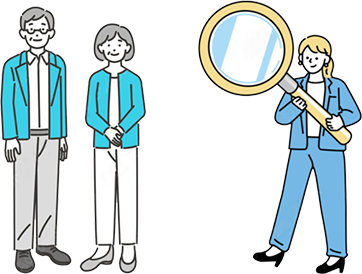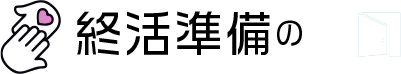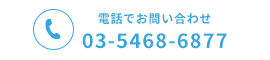ペットを家族同様と思い大切にする家庭は以前よりも多く、飼い主とペットの結びつきは深くなっていく一方の昨今。配偶者を亡くした高齢者がひとりでペットと暮らしているという家もたくさんあるでしょう。
ペットは人間よりも寿命が短いものですが、もし飼い主がかなりの高齢で何かあったとしたら、ペットはどうなってしまうのでしょうか?
飼い主が孤独死するとペットはどうなる…?
ペットの飼い主自身が高齢の場合、ペットよりも先に飼い主が亡くなってしまうことは、残念ながら多々あることです。それも、飼い主にほかに家族がなく、誰にも知られずいわば孤独死してしまうケースも存在します。
ペットは、飼い主がいなければ食事の確保もできず、また外に出ることも不可能です。発見が遅くなればなるほど、ペットも衰弱していってしまうでしょう。食べ物に困って、飼い主の遺体を食べてしまっていたという痛ましい事例もあります。
生き残ってさえいればなんとかなるかというと、そうではない場合もあります。
飼い主に先立たれ、残されたペットはどうなってしまうのでしょうか。
ペットが生きていたら
飼い主が亡くなっていることに第三者が早めに気づくことができれば、ペットは生存したまま見つけられることもあります。
この場合、細かいことを抜きにしても1番多いケースは「親族の誰かが引き取る」というパターンでしょう。故人がかわいがっていたペットを放っておくというのは、人情からもなかなか難しいことだからです。
相続の対象となる
ペットは法律上では「物」として扱われます。つまり、被相続人(亡くなった元の飼い主)の財産と一部ということになり、相続が発生した際にはペットもその対象となります。相続人が複数いる場合は、どの相続人に相続されるかという問題に巻き込まれてしまい、決定するまでの間誰が世話をするのか、という状況にもなってしまいます。
さらに、相続すると生じるのは「所有権が移る」という事実だけです。ある相続人にペットの所有権が移ったとしても、ではその人がきちんとペットをかわいがってくれるかというと、それとこれとは別問題なのです。相続人同士で押し付け合い、仕方なく引き取った相続人のもとに行ったペットが果たして幸せになれるかどうかは、まったく保証がないといえます。
誰も引き取らなかったら
引き取り手がどうしてもいない場合、ペットは保健所に行くことになります。保健所にはさまざまな事情で飼い主と一緒に暮らせなくなった動物が引き取られていますが、いつまでも面倒を見てもらうことは不可能です。新たな飼い主が見つからなければ、最終的には殺処分されることになります。
実際に、飼い主が孤独死したあとに残されたペットは、約60%が殺処分となっているのが現実です。
ペットが死んでいたら
飼い主の死の発見が遅れ、ペットも衰弱死してしまっていたという事例も、残念ながら多くあります。
前述したように、ペットは飼い主たる人間がいなければ生きていくことさえできません。かわいがっていたペットが自分の死後どうなってしまうかということを真剣に考え、打てる対策を万全にしておかなければならないのです。
一人暮らしでペットとの別れ、どんなパターンがある?
高齢者の一人暮らしの場合、ペットを手放さなければならなくなる事情は「飼い主が先立つ」以外にもいくつかあります。その場合でも、ペットの今後の幸せのためには何ができるか考えなければなりません。
飼い主に介護が必要になる
在宅介護であったとしても、介護が必要になる状態にまでいくと、それまでのようにはペットの世話ができなくなる可能性が高いでしょう。自分の生活で手一杯になり、ペットにまで手がまわらなくなる前に、やはりペットの行く先を考えなければなりません。
飼い主が施設に入ることになる
介護の度合いが上がってしまい、自宅での自力の生活が難しくなると、介護施設に入る選択肢も出てくるでしょう。そうなると、飼い主はいなくなってしまうも同然です。飼い主は自分の体の状態を把握し、早めに行動しておくことが必要なのです。
飼い主が別の家族の元で暮らすことになる
飼い主が自分の子世代などと同居することになり、自宅を引き払う場合は、可能であればペットも連れていきたいはずです。しかし同居先の家庭の事情でそれが難しい場合も、やはりペットの未来を考えなければならないでしょう。
ペットとの別れの前に何ができるか
前述したように、ペットが飼い主に先立たれて残されてしまうと、ペットには悲惨な未来が待ち受けることになりかねません。
そうならないよう、飼い主は自分が元気なうちから対策を考えて行動しておかなければならないのです。
大事なペットのために、飼い主は生きている間に何ができるでしょうか。
引き取り手を探しておく
かわいがっているペットと、最期まで一緒にいたい気持ちはもちろんあるでしょうが、親族などから引き取り手を見つけて、そしてまだ自分が元気なうちに託すのがもっともペットのためになるはずです。
ペットにとっては、飼い主が急にいなくなってしまった、新しい飼い主のもとで突然環境が変わってしまった…となると、大きなストレスを抱えかねません。新しい環境に慣れてもらうためにも、生前元気なうちから引き取り手を早めに探していくのがよいのです。
新しい飼い主に安心して引き取ってもらうためにも、ペットに関しての情報は一か所にまとめておくこともおすすめします。名前や誕生日、種類(犬種や猫種など)、性別はもちろんのこと、普段どんなものを食べているか、生活のパターンや性格、かかりつけ医、健康状態といったものも詳しく書き記して「引継書」を作成するとよいですね。
里親を探す
まずはまわりに里親になってくれる人がいないかを探してみます。もっともよいのは、普段からそのペットのことをよく知っている人が里親になってくれることですが、難しい場合はインターネットで里親募集のサイトを活用してもよいでしょう。
また、NPO法人や動物愛護団体に相談して里親を見つけると、さらに安心です。
老犬・老猫ホームに入所させる
人間に老人ホームがあるように、年老いた犬や猫のための施設もあります。病気を持っていたり、老齢だったりするとなかなか引き取り手や里親を探すことも難しい場合が多いので、このような施設の利用も考えるとよいでしょう。
ただし、もちろん費用は相応にかかりますし、普及数はそれほど多くないため、お住まいの地域で見つけるのが難しいこともあります。
ペット可の老人ホームに入所する
飼い主自身が老人ホームに入るとき、ペットも一緒に入所可というところを探すという方法もあります。ただし、こちらも需要に対して供給が追いついているとはいえず、人気が高くてなかなか見つけることは難しいでしょう。やはり費用が高額となりがちでもあります。
また、飼い主自身が存命時は問題ありませんが、飼い主が亡くなったあとまでペットの面倒を見てくれるかというと、必ずしもそうではないホームもあります。その場合は、結局自分の死後ペットをどうしたらいいかということは考えておかなければなりません。
負担付遺贈をする
「ペットの飼育をしてもらう代わりに財産を残す」という約束のもとに、新しい飼い主に飼育費を贈与できる方法です。自分の死後、ペットの飼育には面倒がかかるうえ、金銭的負担もお願いすることになるため、その分を新しい飼い主に財産として渡すわけです。
ペットに遺産を遺すことは法律上不可能ですが、負担付遺贈であれば財産を遺す相手が新しい飼い主という人間であるといえども、間接的にはペットに財産を遺す形になるでしょう。
負担付遺贈をする際には、遺言書を作成することになります。ただ、遺言の効力が発したあとに遺贈された側が「遺贈を放棄する。だからペットも引き取らない」と言い出す可能性ももちろんあります。そのため、一方的に遺言書を残すのではなく、遺贈を考えている相手と生前きちんと話し合いをしておくことが必要です。
負担付死因贈与契約をする
これは前項の負担付遺贈とよく似ていますが、異なる点は「契約である」というところです。負担付遺贈が場合によっては一方的になってしまう可能性があるのに対して、負担付死因贈与契約は生前に受贈者から合意を得て契約を取り交わすことで、受贈者が負担を放棄することを防ぐことが期待できます。また、生前に条件や内容を細かく設定できるという点でもメリットがあるでしょう。
ペット信託を利用する
負担付遺贈や負担付死因贈与と似たものに「ペット信託」があります。
こちらは引き取り先や新しい飼い主との間にペット信託会社を挟み、ペットのために使ってほしい財産を信託会社に預け、信託会社は残されたペットのために新しい飼い主がきちんと世話をしてくれているかどうかを見守るというシステムです。
信託会社がきちんと見守ってくれることで、大きな安心感を得られるというところがメリットですが、その分費用は高額になります。
ペットの未来を考える際の注意点
自然に放つのはダメ
自分が面倒を見られないのなら、自然に放してしまうのはどうかと気軽に考えている人もいるのではないでしょうか。犬や猫はさすがにまずいとしても、鳥やハムスター、うさぎ、爬虫類などの小動物であれば大丈夫なのでは?というのも、大きな勘違いです。
人が飼育する哺乳類・鳥類・爬虫類は「動物愛護管理法」のもと「愛護動物」として守られているため、自然に還す行為は「遺棄」としてみなされ、犯罪となってしまうのです。
また、元は野生動物であったとしても、一度人に飼育されてしまえばもう野生で生きていくことはできません。元が野生動物でなかったのならなおのこと、地域の生態系を一時的にでも狂わせてしまう恐れもあるでしょう。
ペットを自然に放す行為は、絶対にNGだということです。
里親詐欺に注意
里親を探す際に、個人ではなくインターネットを頼る場合、「里親詐欺」にはしっかり注意しなければいけません。残念ながら、ペットを転売目的や虐待目的で里親として名乗りをあげている詐欺集団が紛れ込んでいる場合があるのです。
大切にかわいがってきたペットが、そんなところに引っかかるのは絶対に嫌ですよね。里親募集団体を探す際には、怪しいところはないかしっかり確認してから利用しましょう。
まとめ
家族同様に暮らしてきたペットを、生前のうちから手離すのは切ないことです。しかし自分に万が一何かあったときに悲惨な運命をたどってしまうのは、他ならぬその愛するペットなのです。
ペットのために何ができるかをじっくり考え、できるだけのことをしっかりやってあげることが、ペットへの最後の愛情です。