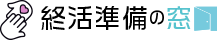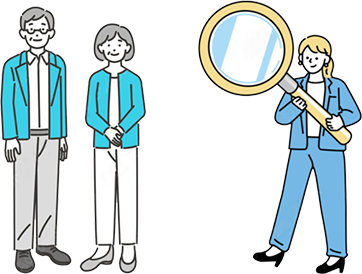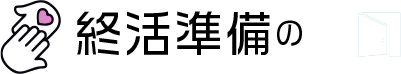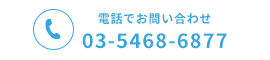遺言書というと、大金持ちが用意するもの、というイメージがあるかもしれませんが、何も莫大な財産がないと縁がないのかといえば、そんなことはもちろんありません。たしかに遺言書に記せる内容は主に財産と相続に関してですが、それによってさまざまな意思を託すことができるからです。
今回は遺言書について、書き方も含め解説していきます。なお、メインとなるのは3種類ある遺言書のうち「自筆証書遺言書」というものです。
遺言書とは
遺言書・遺言状・遺書・エンディングノートの違い
まず、遺言書と遺言状は呼び方の違いだけで、同じものです。財産の分け方について書かれた書類であり、きちんと定義に従って書くことで法的効力を持ちます。
一方、遺書とエンディングノートには法的効力がありません。
遺書は主に、亡くなる間際に自分の気持ちを親しい人に綴ったいわば「手紙」です。したがって内容は財産の分け方だけに限りません。
エンディングノートは、近年よく知られてきたもので、遺書よりもさらに自由にさまざまな内容を書き記しておくものです。家族や友人への想いだけでなく、財産の内容や葬儀の形式の希望、インターネットサイトなどのパスワード、とにかく何でも記録して、遺族が困らないように用意しておけます。ただしどんなに希望を書いても、法的拘束力はないため、遺族がそれをすべて叶えてくれるとは限りません。
遺言書を遺すメリット
遺言書がなくても、法定相続という制度があるため、相続自体は行われます。しかし、何か特定の希望がある場合、遺言書を作成しておくことで被相続人の意思を生かすことができるのです。
相続争いを避けられる
遺言書の効力により、財産の相続の決定には一定の拘束力が生まれるので、相続人同士で無駄な相続争いが起きることを防ぐことができます。
法定相続人以外にも相続させられる
血のつながりがないけれども生前大変お世話になった人にも財産を遺したい、などというときには、遺言書にしっかりその旨を記載することによって可能となります。
相続人がいなくても財産の行き先の希望を反映させられる
身寄りがなく、相続人となる人もいない場合、個人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。それを良しとせず、特定の団体に遺贈寄付をしたい、など財産の行き先を自分で決めたい場合にも、遺言書が有効です。
遺言書で決められること・効力
誰に何を遺すのか
自分の財産を、誰にどのくらい遺すのかを決められます。法定相続人ではない人に財産を分けることも可能です。
本来ある相続人の権利を剥奪できる
法定相続人として財産を相続できる権利を持つ人から、それを剥奪できる、つまり財産を相続させないようにすることもできます。たとえばその相続人から生前虐待を受けていたなどというケースで有効です。
遺言執行者を指定できる
遺言執行者を誰にお願いするか、ということを決められます。一般的には弁護士などを指定することが多く、これによって遺言の執行が速やかに進むというメリットがあります。
隠し子を認知できる
生前認知されていなかった隠し子の認知も、遺言書で可能となります。その子どもは認知されることによって、相続人としての権利を得られることになります。
保険金の受取人を変更できる
生命保険金の受取人を変更することができます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言を遺す人が自筆で作成する遺言書です。財産目録だけはパソコンなどで作成してもかまいませんが、その他の部分は必ず遺言者本人の自筆でなければなりません。
自筆証書遺言書について、詳しくは後述します。
自筆証書遺言のメリット
費用をかけることなく、また何度でも内容を書き直せるため、手軽に作成し始めることができます。内容を他人に知られないようにしておくことも可能です。保管は自己の責任で行います。
自筆証書遺言のデメリット
定められた要件を満たしていないと、遺書として無効になってしまいます。保管は自己責任であるため、紛失してしまう、遺言書の存在自体を知られない、忘れられてしまうという恐れもあります。気軽に作成できる分、きちんと遺言書としての使命を果たせるかという保証が少ないといえるでしょう。
自筆証書遺言が無効となる事項
被相続人が亡くなったあと、相続人は遺言書を勝手に開封してはいけません。遺言書の内容が無効になってしまうので、家庭裁判所に提出して「検認」を受ける必要があります。
ただし、法務局で遺言書を保管してくれる「自筆証書遺言保管制度」を使えば、検認は不要となります。詳しくは後述します。
また、自筆証書遺言は定められたルールに従って書かないとやはり無効になってしまいます。これに関しても次項以降で詳しく解説します。
公正証書遺言
遺言を遺す人と証人2人以上が公証役場において公証人に遺書の内容を伝え、公証人がそれをまとめて公正証書として作成する遺言書です。原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット
公証人が記述してくれるため、遺言書の様式に不備があって無効になる可能性は、自筆証書遺言に比べて格段に低くなります。
また、原本は公証役場で保管してもらえることで、紛失や偽造の恐れもなくなります。
公正証書遺言のデメリット
費用がかかること、公証役場まで出向く手間があることが、強いてあげるならデメリットでしょうか。費用も手間も、安心のためだと考えればデメリットにはならないかもしれませんね。
秘密証書遺言
遺言書の内容自体は誰にも知られないようにし、存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらうという遺言書です。あまり多く用いられることはありません。
遺言書(自筆証言遺書)の書き方
ここからは、3種類ある遺言書のなかでも特に「自筆証書遺言」の書き方について細かく解説します。
自筆証書遺言が有効となる5つの要件
前述したように、自筆証書遺言は決められたルールがあり、それに沿ったものでないと遺言書としての効力が認められません。ルールは5つあり、すべてを満たしている必要があります。
全文自筆である
自筆証書遺言書は、全文を遺言者本人が自筆しなければなりません。パソコンで作成したり、代筆してもらったりすると無効になります。
財産目録だけは自筆でなくても問題ないとされていますが、その際も自筆でない部分の添付書類にはすべて署名押印が必要となります。
作成した日付を正確に明記する
年・月・日を正確に記します。「◯月吉日」のような書き方は無効となる、ということです。
もし複数の遺言書が存在する場合、新しい日付のものが有効となります。
署名する
遺言書本人の署名が必要です。
押印する
署名だけでなく、押印も必要です。認印でもかまいませんが、実印の方が信頼性が高いといえるでしょう。
訂正の仕方を守る
訂正の仕方にも厳格なルールがあります。まず間違えた部分は二重線で消し、正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れます。さらに余白部分に「2字削除、4字加入」のように書いて署名押印します。塗りつぶしたり、修正ペンなどを使ってはいけません。
訂正のルールは非常に細かいため、訂正箇所が多い場合は、初めから遺言書自体を書き直したほうがいいともいえます。
自筆証書遺言書の書き方の流れ
必要書類を集める
財産の内容をきちんと把握するためにも、次のような書類を用意しましょう。
・不動産登記簿
・預貯金通帳
・生命保険証書
・証券会社などとの取引資料
・絵画や骨董品などの明細書
財産目録を作成する
どのような財産があるかという「一覧表」が、財産目録です。この部分だけは自筆でなくてもよく、また預貯金通帳の写しなどを添付資料とするのも可能です。ただし、それらには署名と押印は必要となります。
誰に何を遺すか明記する
曖昧な書き方をせず、金額や内容をはっきりと記しましょう。せっかく遺言書を用意しても書き方によってトラブルの種になってしまっては意味がありません。
「任せる」「託す」「渡す」「譲る」といった語は避け、「相続させる」「遺贈する」「取得させる」などのはっきりとした言葉を選ぶことも重要です。
自筆証書遺言書保管制度とは
2020年7月10日からスタートした制度で、自筆証書遺言書を法務局が預かってくれる、というものです。この制度が発足したおかげで生じるメリットは以下のような点です。
紛失や盗難を防げる
自筆証書遺言書は手軽に書ける分、紛失や盗難の恐れが絶えません。この制度では遺言書の原本と画像データを法務局で保管してもらえるため、紛失や盗難のみならず偽造や改ざんに遭うことも防げます。
無効な遺言書になる可能性が低くなる
自筆証書遺言書には定められた形式があり、それを守っていないものは無効となってしまいますが、この制度を使うと法務局が遺言書をチェックしてくれます。形式に沿っているかどうかということを確認してくれるため、自分ひとりで遺言書の作成を進めるよりも無効な遺言書になる可能性が低くなるといえます。
相続人が見つけやすい
自筆証書遺言書の場合、遺族が見つけられない、忘れ去られてしまう、ということも起き得ます。その点この制度を使っていれば、遺言者があらかじめ希望している場合、遺言者の死亡が確認されたら法務局から遺族に通知が行くので、遺言書が発見されないという事態を防ぐことができます。
検認手続きが不要になる
前述したように、自筆証書遺言書は遺言者の死後、遺族が勝手に開封してはならず、家庭裁判所で検認というものを受けなければなりませんが、保管制度を利用しているとこの検認手続きも省略することが可能になります。
遺言書を書くときに気をつけるポイント
複数人共同での遺言は無効
遺言書はひとりにつき一通が必要となるため、一通に「夫婦共同」などとして2人分の遺志を記載したような遺言書は無効となります。
音声での遺言は無効
音声による遺言、ビデオレターによる遺言も無効です。遺言は、書面によってなされなければなりません。
遺留分侵害に注意
遺留分とは、相続人が本来相続できる正当な分け前のことです。これは遺言書でも覆すことができない部分です。
たとえば、本来配偶者は財産の2分の1を相続することができますが、遺言書には「愛人に全額相続する」と書かれていたとしましょう。その場合、配偶者は愛人に対して財産の2分の1である遺留分を請求することができるのです。これを遺留分減殺請求といいます。
遺言書があっても、遺留分請求があると結局配分が変わってしまい、ほかの相続人の相続分に影響を及ぼす恐れも出てきます。そのため、初めから遺留分についてはきちんと想定したうえで遺言書を作ることが大事です。
書き換えは可能
遺言書の内容は、あとから書き換えることができます。まずは今現在の気持ちを書き出してみることから気軽に始めてみるのもよいでしょう。
ただし、正式に書き上げたあとの書き換えは、法律に定められた規定にしたがわなければならないので、その点は注意が必要です。
まとめ
遺言書、特に自筆証書遺言書に関しては、比較的気軽で手軽に書き始めることができるため、「遺言書は難しくてかしこまったもの」というイメージが少しは薄れたのではないでしょうか。もちろん、決められたルールを守らなければなりませんが、まずは書いてみて、心配な点は弁護士などの専門家に助言を受けるというのもよいでしょう。