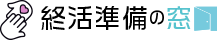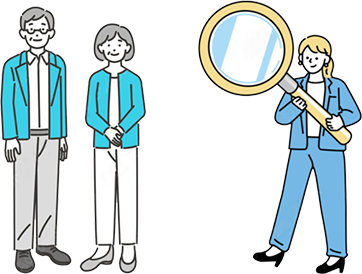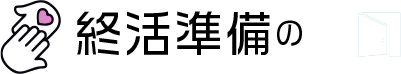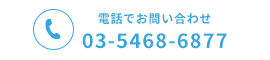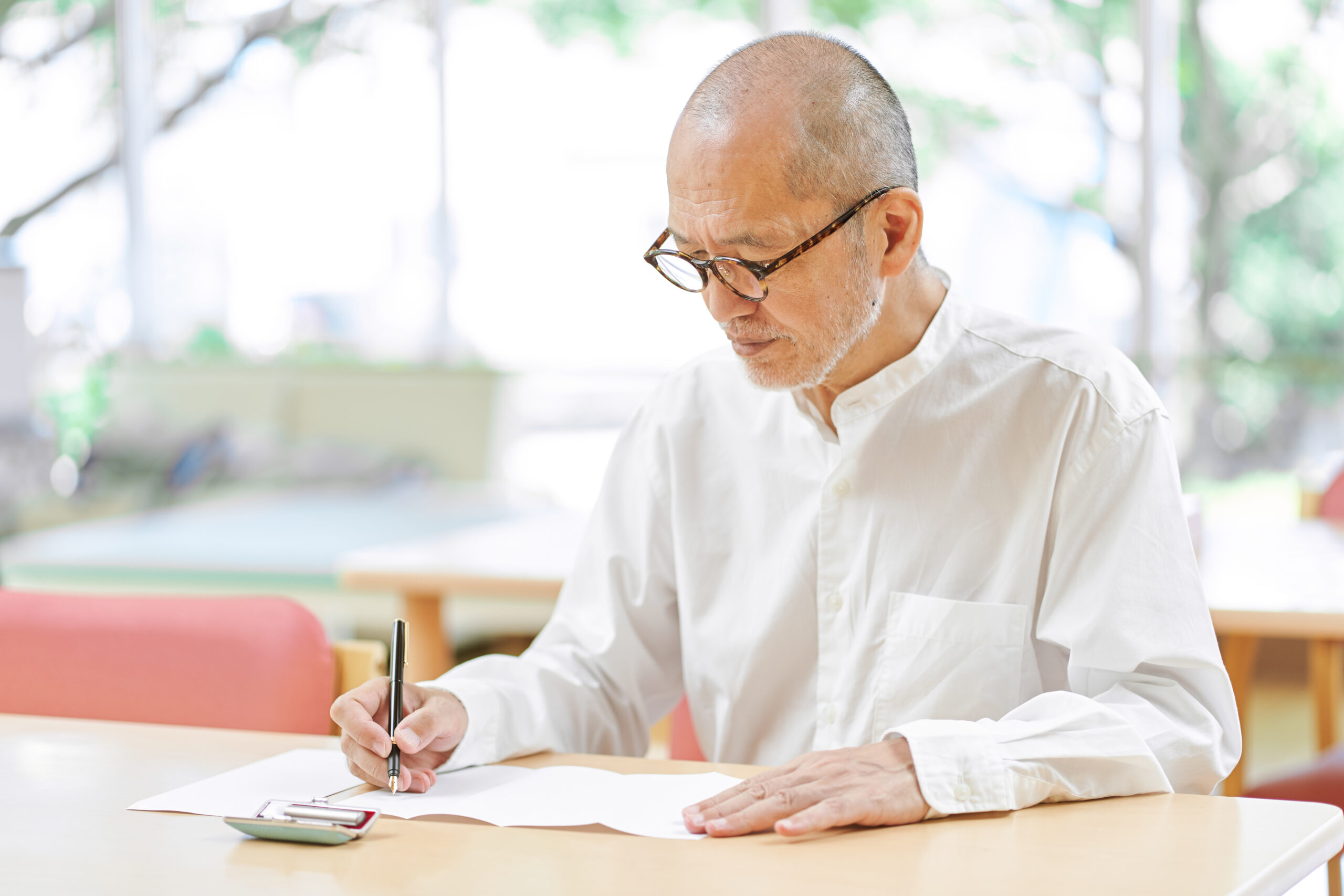財産相続というと、メリットばかりあるようなイメージを抱きがちですが、果たしてそうなのでしょうか。実は、借金などのマイナス資産も相続の対象となるため、被相続人にプラス資産よりマイナス資産の方が多かったなどの場合、「どちらも相続しない」という選択をするのがよいケースもあるのです。これを「相続放棄」といいます。
とはいっても、相続を放棄することにためらう気持ちが出てくることもあるでしょう。相続の権利があるのに、それを手放してしまうということには勇気がるものだからです。
そこで今回は、相続放棄の内容や手続き方法、最善であるケースや注意点について解説していきます。
相続について選べる3つの方法とは
まずは今回のテーマとなる「相続放棄」とともに、相続が発生した際に選べる選択肢について「単純承認」と「限定承認」についても理解しておきましょう。
単純承認とは
いわゆる「一般的な相続」です。プラスの資産(現金や不動産・有価証券など)も、マイナスの資産(借金や保証債務など)も、すべて相続することです。
「限定承認」や「相続放棄」の申述を定められた期限内に行わなければ、自動的に単純承認を選択したものと判断されます。
限定承認とは
「プラスの資産を限度に、マイナスの資産も相続する」という方法です。
限定承認が有効なケースは、たとえば「どうやら故人には債務があるようだが、どのくらいあるのかまではわからない。しかしプラスの資産があることも確実である」というような場合です。単純承認だと、相続したあとに万が一債務が見つかった場合は、それも相続しなければなりません。しかし限定承認を選択していれば、債務の返済額はプラスの資産で得た金額を限度とするのみにできます。したがって、マイナスの資産がプラスの資産よりも多くなってしまう、という事態を避けることが可能なのです。
また、借金はあるものの、形見として残したいものがある場合にも、限定承認は有効です。
たとえば、借金が500万円と、100万円のダイヤモンドがあるとしたら、借金を100万円返済することでダイヤモンドは手元に残せます。借金500万円のうち、プラスの資産であるダイヤモンドの価値100万円の範囲でマイナス資産の負担を引き継いだ、ということになるのです。これは「資産となる家に親と同居していて、その家にそのまま住みたい」「家宝として受け継いできたものだけは残したい」などのケースでも有効といえます。
ただし、限定承認を選択する場合は相続人全員が限定承認する必要があります。単独で行うことはできないので、相続人が複数いてそのうちのひとりでも限定承認に反対する人がいる場合は、単純承認か相続放棄しか選べない、ということになります。したがって、相続人同士の仲が良好ではない場合は、選択が難しいといえます。
相続放棄とは
今回のテーマである相続放棄は、「プラスの資産もマイナスの資産も、すべてひっくるめて相続を放棄する」という方法です。言い換えると、相続財産に対する権利も義務も一切引き継がないということです。
相続放棄のためには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述します。
ポイントとなるのは、相続放棄が認められると、その相続人は「初めから相続人ではなかった」とみなされる、という点です。そうすると、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった人に相続権が移ったりします。つまり遺産分割協議に参加する権利も義務もなくなり、「代襲相続」も起きなくなります。
次項以降では相続放棄のメリットもデメリットも両方解説しますが、相続人の状況によってどちらが大きいかは異なるため、放棄するかは慎重に検討して判断する必要があります。
マイナスの資産「だけ」を相続放棄することは不可能
上記のことを踏まえると、相続をする際に「プラスの資産だけを引き継いで、マイナスの資産は放棄する」ことは不可能だということです。当然のことではありますが、十分理解しておきましょう。
もし被相続人に借金があった場合、相続人が相続放棄もせず借金の返済もしなかったとしたら、相続人に督促の連絡が来ることになり、最終的には財産差し押さえにまで発展してしまいます。このとき差し押さえられるのは、被相続人の財産だけではなく、相続人の財産までも対象となります。相続に無関心で放置していると、思わぬところで被相続人の多額の借金を知り、その責任を負うことにもなりかねません。相続放棄や限定承認についての知識は、しっかり押さえておく必要があるのです。
相続放棄を選んだ方がよいケース
明らかにマイナス資産が多い場合
資産・財産というと、プラスになるもののイメージがつきまといがちですが、借金のような負債も資産に含まれるものです。
もし故人に多額の借金や債務があった場合や、故人が誰かの連帯保証人になっていた場合など、明らかにプラスの資産(現金や不動産など)よりもマイナスの資産が上回っていると確認できているケースでは、相続放棄をすることで、故人のマイナス資産を背負わされることを避けられるのです。
遺産相続トラブルに巻き込まれたくない場合
遺産相続の手続きは、大変な手間と時間がかかるものです。相続人同士の仲が悪かったり、そもそも財産が少なくて分け合うことが難しかったり、というような場合は、特にトラブルに巻き込まれやすく、体力も気力も消耗しがちです。
このような事態から逃れることも、相続放棄をすれば可能になります。相続放棄をすると初めから相続人ではなかった、という扱いになるため、遺産分割協議にも関わらずに済むのです。
特定の相続人にすべて相続させたい場合
相続放棄をして相続人の数が減ると、ほかの相続人の誰かひとりに財産を集中させられることも可能です。たとえば、事業を長男が承継するというケースで、債務を長男に集中させれば、ほかの相続人に債務の負担をかけないようにする、ということができます。
ただ、この方法を考える際には、自分ひとりだけでなく他の相続人も協力して相続放棄を検討しなければ意味がなくなってしまいます。
相続放棄をする際の手続き
相続放棄手続きを自分で行ってもよいケースとは
相続放棄をする手続きは、非常に難しくて困難というわけではないので、自力で進めていこうと思う人は多いでしょう。
以下のような条件に当てはまるのであれば、自分自身で手続きを行うことに特に問題はないはずです。
・マイナス資産の方がプラス資産よりも多いことが明確である
・相続放棄の期限までに余裕がある
・財産のなかに不動産がない
・ほかの相続人との関係が良好である
・日常生活を送りながら手続きを進める時間的余裕がある
このような条件がそろっていれば、自力で手続きを進めていっても難題にぶつかることはあまりないはずだといえます。
相続放棄手続きを専門家に依頼した方がよいケースとは
前項とは反対に、専門家に相談もしくは手続きの依頼をした方がよいケースもあります。
・財産関係が複雑で把握し切れない
・限定承認と相続放棄のどちらにするかの判断に迷うような不明確な要素がある
・財産に不動産が含まれている
・居住地や時間的余裕の関係で手続きを進めるのが困難である
・ほかの相続人との関係が良好でなく、調整するのが困難である
簡単にいうと「法律の専門知識を必要とする判断に迫られている」「自分で手続きを進められる時間がない」というケースにまとめられます。
また、自分で手続きを進めていっても、書類に不備などがあると裁判所に直接来るように呼び出しがあったり、申述を却下されたりという恐れがあります。このような状況を想像すると、自分ひとりで手続きを進める限界を感じることもあり得るでしょう。
専門家に手続きを依頼すると、もちろん報酬としての費用は発生しますが、それに見合うだけのものはあるはずです。コストパフォーマンスをよく考えて検討してみることが必要です。
相続放棄手続きを自分で行う際の手順と流れ
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。手続きの流れを順に見ていきましょう。
1.遺言書の有無・内容の確認
遺言書がある場合は、マイナスの資産を自分が引き継ぐとは限らないこともあります。内容によっては負債を相続しないということもあるので、まずは遺言書の内容をしっかり確認することから始めましょう。
2.財産内容の調査・本当に相続放棄すべきかの検討
相続放棄をすべきかどうかを検討するために、綿密に行うべき過程です。相続放棄してしまってから、実はマイナスの資産よりもプラスの資産の方が多かった、などということがわかっても、原則として放棄の撤回はできないので、慎重に行いましょう。
財産内容が複雑で調査が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に調査を依頼するとよいでしょう。
3.相続放棄のための必要書類を集める
必要書類は、相続放棄を申述する相続人が被相続人とどのような関係にあるかによって異なります。共通して必要な書類は以下の通りです。
・相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロード可能)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
・相続放棄を申述する人の戸籍謄本
4.相続放棄のための費用を用意する
自分で相続放棄の手続をする場合にかかる費用は、以下の通りです。
・収入印紙代(申述人ひとりにつき800円)
・連絡用の郵便切手代(管轄の裁判所によって異なるが、一般的には400~500円)
・戸籍謄本などを取得するための代金
これらの金額はさほど大きなものではありませんが、書類収集のためにかかる交通費など、未確定のものもあります。
5.相続放棄申述書を作成する
相続放棄申述書に必要事項を記入します。不備があると受理されず、書き直しとなり余計な手間がかかってしまうので、慎重に作成しましょう。記載内容は難しいものではないので、記載例を見ながら記入すればまず問題はないでしょう。
6.申述書を家庭裁判所に提出する
前述した通り、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と添付書類を提出します。
7.家庭裁判所から送られる「照会書」に回答し返送する(ない場合もある)
申述書を提出すると、場合によっては家庭裁判所から「照会書」という書類が送付されてきます。内容はいくつかの質問から成り立っていて、それに回答して返信する必要がありますが、回答内容によっては申述が却下される可能性もあるため、注意が必要です。
8.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
申述書の内容、または照会書の回答に問題がなければ、1週間~10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで相続放棄の申述が受理されたことになります。
通知書は紛失してしまうと再発行ができないので、大事に保管しましょう。
9.相続放棄受理証明書の交付(必要があれば)
債権者などへ相続放棄したことを証明する際には、上記の受理通知書で足りない場合もあります。これに備えて「相続放棄申述受理証明書」も取得しておきましょう。また、不動産の相続登記の際などにも証明書が必要となります。
受理通知書に証明書の申請用紙が同封されているので、別途申請しましょう。
相続放棄の期限は3ヶ月(=熟慮期間)
相続放棄の申述には期限があり、「相続の開始を知ってから3か月以内」に行わなければなりません。これを「熟慮期間」ともいいます。この期間内に相続放棄の申述を行わなければ、原則として相続放棄は不可能となります。
人が亡くなると、気持ちの整理やするべき手続きなどで、3か月はあっという間に過ぎてしまうでしょう。必要な書類を集めるのに時間がかかったり、予期せぬ不備があったりということも考えられるので、余裕をもって手続きを進めていかなければなりません。
※「相続の開始を知ってから=被相続人が亡くなった日」ではない?
「相続の開始を知ってから」というのは、「自分が相続できる財産があると知った日から」の意味です。一般的には被相続人の死亡の事実を相続人が知るのは亡くなった当日や、訃報を聞くのが多少遅くなったとしても数日後だと考えられるため、「相続の開始を知ってから≒被相続人が亡くなった日」ともいえますが、相続人が疎遠であり、被相続人の死亡をかなりあとになってから知る、というケースもあります。
また、相続人の誰かが相続放棄し、次の順位の相続人に相続権が移ったケースではどうでしょうか。もし熟慮期間が「被相続人が死亡してから3か月」と規定されていたとしたら、相続権が移ったときにすでに被相続人死亡から3か月経過していると、次順位の相続人は相続放棄の選択ができなくなってしまう、という事態になってしまいます。
したがってこの場合、「先順位の相続人が相続放棄したことを知った日」から3か月が、次順位の相続人の熟慮期間、という計算になるわけです。
3か月を過ぎてしまうことがあらかじめ予想されるときはどうするか
早めに準備を始めたにもかかわらず、期限の3か月以内に相続放棄の申述が間に合わないこともあるでしょう。たとえば財産調査がなかなか進まず、相続放棄をすべきかどうか迷っている、戸籍謄本の入手が困難でまだ集められていない、などのケースです。
この場合は、3か月の期限を過ぎてしまう前に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を家庭裁判所に行えば、期間を延長することが可能になります。したがって、相続放棄の申述が3か月以内に終わらないのではないか、という可能性を感じた段階で、すぐに延長申請をすることを検討したほうがよいでしょう。
また、もうひとつの対処方法は、まず「相続放棄申述書」だけでも先に提出してしまうことです。
相続放棄の手続きには、この申述書のほかにも「被相続人の住民票除票または戸籍謄本の附票」「相続放棄を申し立てる人の戸籍謄本」「収入印紙」「連絡用郵便切手」が必要となりますが、戸籍謄本の収集が間に合わなかったときなどは申述書のみ先に提出し、戸籍謄本は追って提出する旨を家庭裁判所に伝えれば、申述は期限内になされたという扱いになります。
期限内に間に合わないと焦らずに、適切な対処をすることで無事申述は済ませられるはずです。
3か月を過ぎてしまった場合はどうなるか
延長手続きもせず、期限である3か月を過ぎてしまった場合は、原則として相続放棄することは不可能になります。よほどの事情があればこの限りではありませんが、非常にハードルの高い手続きとなってしまうため、やはりしっかりと期限内に手続きが終わるよう進めていくべきといえるでしょう。
相続放棄をする際の留意点
相続放棄をすると基本的に撤回はできない
家庭裁判所に申し立てた相続放棄が認められたあとは、基本的にそれを撤回することは不可能になります。やっぱり気が変わった、実はプラス資産のほうが多かったから放棄したくなくなった、などの理由では撤回はできません。
「基本的に」ということは、例外も一部存在するということです。たとえば脅迫された、だまされた、未成年が法定代理人の同意なく手続きをした、などという「やむを得ない」事情があれば、撤回を認められるケースもあります。
しかし、いずれにしても相続放棄は「相続人である権利をすべて失う」という重大な手続きであることは間違いありません。あらかじめ被相続人の財産調査は綿密に行い、本当に放棄してよいのかどうかということは、慎重に判断するべきだということがわかりますね。
相続放棄が認められないケースとは
熟慮期間を過ぎてしまった場合
先述したように、熟慮期間とは相続放棄の申述を行う期限である3か月間のことです。詳細も先述したように、この期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなります。何か正当な理由がある場合はこの限りではありませんが、「正当な理由」に自分の事情が該当するかどうかは、弁護士などの専門家ではないと判断がつかないほど難易度の高いものなので、相談することを検討しましょう。
たとえば「被相続人が亡くなったことを知らなかった」「相続財産はないと思っていて、そう信じるに足る相当な理由があった」などという理由が例として挙げられます。
相続放棄前に遺産を処分してしまった場合
遺産の「処分」とは、次のような行為です。
・財産である現金を使った
・不動産を売却した
・家屋を取り壊した
・故人の預貯金の払い戻しをした
・故人の借金の一部でも返済した(利子も含む。ただし返済時に使った財産が故人ではなく相続人自身のものであれば問題なし)
・経済的に価値のあるものを形見分けした
相続放棄の申述をする前に遺産の処分を一部でもしてしまうと、先述した「単純承認」をしたと判断されてしまい、相続放棄はできなくなります。
また、遺産を隠した場合にも単純承認が成立したとみなされ、相続放棄は不可能になります。
ちなみに、葬儀費用は相続財産とはみなされないため、被相続人の預貯金口座から葬儀費用を支払っても、遺産処分とは判断されません。
その他こんな場合にも
すでに遺産分割協議書に署名・捺印してしまっている場合も、相続放棄はできなくなります。相続放棄をすると、相続の順位が変わり、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、もともと相続権がなかった人に相続権が移ったりすることもあるので、それまで行った遺産分割協議が無意味となってしまいます。協議書に署名・捺印した時点で自分は相続人であると認めることになるため、この後の相続放棄は不可能です。他の相続人にも多大な迷惑をかけるので、遺産分割協議を始める前に相続放棄の手続きをするべきといえるでしょう。
また、祭祀財産といって、墓石や仏壇・家系図なども相続放棄の対象外となります。
基礎控除額は変わらない
相続税の計算をする際には、「基礎控除額」という概念があります。簡単にいうと、相続財産の評価額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告・納付の必要はなくなるのです。
この基礎控除額の計算式は「基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数」であるため、基本的には相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなるわけです。
では、相続放棄をすると「最初から相続人ではなかったものとして扱われる」のだから、基礎控除額の計算にも影響が出るのではないか?という疑問が浮かぶところですが、実はこの点には問題がありません。相続税の計算をする場合においては、「相続放棄がなかったもの」として扱われるからです。
相続放棄をした相続人がいるからといって、基礎控除額が減ってしまうということはないので、ある意味安心ですね。
相続開始前や被相続人の生前に相続放棄はできない
被相続人の生前のうちから、相続人が相続放棄をすることはできません。「被相続人が多額の借金を背負っているということを知っているから、相続は放棄する」という心づもりがあったとしても、生前のうちに何か法的効力のある手続きはできないのです。
相続放棄によって相続権が移動し、それがトラブルのもとになる恐れがある
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」という扱いになるため、次の順位に相続人がいる場合はその人に相続権が移ります。
そのとき、もし相続放棄をした人がその事実を次順位の相続人に伝えなかったとしたら、どうでしょうか。財産のなかに多額の借金があったら、次順位の相続人にその負担がのしかかることになり、そこからトラブルにつながる可能性は十分考えられるのです。
相続放棄は限定承認と違って、相続人がひとりで手続きを進めることができてしまいます。しかしトラブルを未然に防ぐためには、相続放棄を検討し始めたときにほかの相続人にもきちんと話をしておくべきだといえます。
相続人全員が相続放棄をすると財産は国のものになる
もし、相続人全員が相続放棄を選択すると、その財産はどこへ行くことになるのでしょうか。
この場合、家庭裁判所によって選任された「相続財産管理人」が相続人の代わりに財産の調査・処分・清算をすることになります。法定相続人ではない「特別縁故者(たとえば故人の世話をしていた人など)に分与されることもありますが、それでも残った財産がある場合には、最終的に国に帰属します。
相続財産管理人が選任されるまでは相続人に財産の管理義務がある
全員が相続放棄をして、上記の「相続財産管理人」が選任されることが決まっても、管理人が実際に管理できる状態になるまでは、相続人にその財産の管理義務は残ることになります。
死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金は受け取れる?
相続放棄をすることで遺産は受け取れなくなりますが、死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金は、場合によっては受け取れることがあります。
まず、被相続人が契約時に決めていた「受取人」が、被相続人本人である場合。これは相続財産の一部とみなされ、相続放棄した人は受け取れません。もしくは受け取ってしまうと「単純承認」となってしまう恐れがあるため、注意が必要です。
対して「受取人」が特定の相続人であった場合。これは被相続人ではなくその相続人の財産として権利があるため、相続放棄していても受け取ることができます。ただしこのケースは、税法上では「みなし相続財産」というものになるので、相続税はかかることがあるという点に留意しておかなければなりません。
相続放棄と財産放棄の違い
相続放棄とよく似た言葉に「財産放棄」というものがあります。こちらは法律上の用語ではなく、遺産分割協議で慣例的に使われている言葉で、要するに法的効力は何も持たない行為です。
財産放棄はまた、「相続分の放棄」といういい方もします。ますます「相続放棄」と似ていてややこしいため、違いを理解しておきましょう。
財産放棄(相続分の放棄)とは何か
財産放棄は、遺産分割協議においてほかの相続人に「私は財産を相続しません」という意思表示をすることで、家庭裁判所に何か手続きを行うわけではないため、相続放棄と違って法的な相続権自体は失われません。
相続放棄が「最初から相続がなかったものとして扱われる」のに対し、財産放棄は「相続人としての地位はそのままである」という点が大きく異なるのです。この点は、次項のメリット・デメリット両方につながります。
財産放棄のメリット・デメリット
相続放棄ではなく財産放棄をすることで得られるメリットは、まず財産を放棄しても「相続権の移動はない」という点です。
たとえば被相続人の子が全員相続放棄すると、その相続権が次の相続順位である被相続人の親や祖父母、兄弟姉妹に移ってしまいますが、財産放棄ではそれを免れることができます。前述したように、相続権の移動によって起きうるトラブルを回避できることにもつながるでしょう。
また、家庭裁判所を通さずに財産を放棄できるため、手間や費用を抑えられるという点もメリットといえます。
デメリットは、まず財産放棄する旨について、遺産分割協議においてほかの相続人からの同意が必要だという点です。ここで何らかの理由で揉めてしまうと、財産放棄は不可能となってしまいます。
さらにもっとも大きなデメリットとして「負債の相続は免れない」というものが挙げられます。財産放棄はあくまで相続人同士で有効な契約であるため、もし財産に債務が含まれていた場合、債権者がそれを認めるかどうかは別問題だということです。
たとえば被相続者の子Aが財産を放棄する、と遺産分割協議で意思表示をして、子B・子Cが財産も負債も引き継ぐと決めていても、債権者は子Aにも請求することが可能なのです。
したがって、負債を免れることが目的であるなら、財産放棄ではなく相続放棄をしなければならないということになります。
相続放棄と代襲相続の関係
「代襲相続」とは、「相続発生時に、本来なら相続人となるはずだった人がすでに死亡していた場合、その相続人となるはずだった人の子が代わりに相続する」というものです。
たとえば、被相続人(A)に子(B)と孫(C)がひとりずついて、被相続人が死亡して相続が発生した時点ですでに子が死亡していた、という場合、被相続人の財産は孫に相続されることになります。
この代襲相続という制度が、しばしば相続放棄と並べられて説明されることがあります。上記のケースでいえば、「子が死亡しているから孫に相続されるのであれば、子が生存していて相続放棄した場合も孫に相続されるのではないか」といった具合にです。
しかし、相続放棄はそもそも「元から相続権はなかった」という扱いになるため、子が相続放棄をした段階で孫もその相続とは関係がなくなる、つまり被相続人からの相続は孫には発生しません。
この点は、混同しないように注意が必要です。
ただし、相続放棄と代襲相続が重なる場合もあります。
同じく上記のケースで「被相続人(A)よりも子(B)が先に死亡し、孫(C)が相続放棄をした」という場合には、CはBの財産を相続しませんが、Aとの祖父-孫関係はなくなったわけではないため、BのあとにAが死亡したならば、CはAの財産を代襲相続することは可能である、ということになるのです。
まとめ
「遺産の相続」というと、自身にとってプラスになるイメージが大きいものかもしれませんが、相続する資産にはマイナスのものも含まれています。まずこの点をきちんと理解しておかないと、ろくに故人の財産内容を調査することもせず、相続方法の選択をする前に期限が来てしまって単純承認せざるを得なくなってしまい、フタを開けてみたら莫大な借金を負うことになってしまっていた、ということにもなりかねません。
相続放棄の手続きだけでなく、遺産相続においてはさまざまな過程があり、煩雑さが伴います。わからないことは調べ、できることから早めに着手していきましょう。