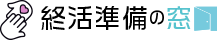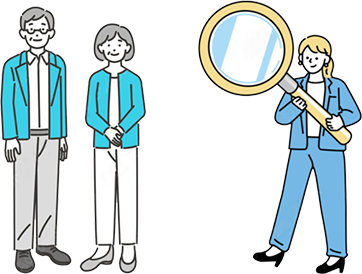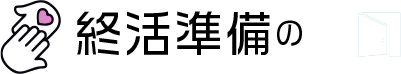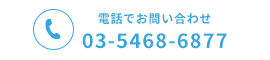遺産相続の手続きは面倒で大変なことが多い、というイメージがつきまとうものです。多くの不慣れな手続きを期限内で行う必要があり、これまた聞き慣れない専門用語を理解しなければならず、しかも手続きの間に相続人同士で何か意見の不一致やトラブルがあった場合は、相当な時間や手間がかかる、という不安や懸念があるからでしょう。
こういった負担を少しでも軽くするためには、遺産相続についての手続きはまず何から始めたらいいのか、どのように進めていくのか、注意する点はどんなことか、というようなことをあらかじめ理解しておくと、スムーズに事を運べるはずです。
今回は遺産相続の手続きについて、時系列に、期限を提示しながら解説していきます。
遺産相続の手続きの流れ(項目のみ)
まずは、被相続人(財産を遺して亡くなった人のこと。以下、「故人」と記します)が亡くなったら行うべきことを、ざっと順番にリストアップします。厳密には直接の相続手続きとなるものでなくとも、その後に続く相続手続きのために必要なことも記載しています。さまざまな事柄を時系列で記載しているため、遺産相続に直接つながる手続きには☆マークを記しています。
また、「なるべく」と書いてある手続きは、期限は特に存在しないものの、やはりその後の手続きのためにはその期限内のうちに早めに行っておくべきものです。たとえば「7日以内」という項で「なるべく」と書かれている手続きは、できるだけ7日以内に行ったほうがよいものという意味です。
7日以内に行うこと
死亡診断書・死体検案書の受取
死亡届の提出
火葬許可証の取得
遺言書の有無の確認(なるべく)☆
検認の請求(なるべく)☆
10日以内に行うこと
年金の手続き
14日以内に行うこと
健康保険の手続き
介護保険の手続き
世帯主変更届の提出
金融機関の口座凍結の手続き(なるべく)☆
公共料金などの解約・名義変更(なるべく)
1ヶ月以内に行うこと
雇用保険の手続き
遺産相続人の調査・確定・戸籍謄本などの取得(なるべく)☆
相続財産の調査・確定(なるべく)☆
3ヶ月以内に行うこと
相続放棄や限定承認の申述☆
4ヶ月以内に行うこと
所得税の準確定申告☆
遺産分割協議の開始・遺産分割協議書の作成(なるべく)☆
10ヶ月以内に行うこと
相続税の申告・納付☆
相続財産の名義変更や換金(なるべく)☆
1年以内に行うこと
遺留分侵害請求☆
2年以内に行うこと
埋葬料請求
葬祭費請求
高額医療費の還付請求
3年以内に行うこと
相続登記(不動産の名義変更)☆
生命保険金の受取☆
5年以内に行うこと
遺族年金の請求
故人の未支給年金の請求
遺産相続の手続きの流れ(詳細)
次に、前述した手続きの内容について詳しく解説していきます。こちらも、遺産相続に直接つながる手続きには☆マークを記しています。
7日以内に行う手続き
死亡診断書・死体検案書の受取
被相続人(財産を遺して亡くなった人のこと)が亡くなって速やかに行うべきは、まず「死亡診断書」を取得することです。死亡診断書は、死亡の事実を医学的・法律的に証明するためのものであり、病院で亡くなったりかかりつけ医がいたりした場合は、医者が発行します。
事故死・突然死・不明死などの場合は、警察による検死後に交付される「死体検案書」が、死亡診断書と同等のものになります。
これらの書類は、その後のさまざまな手続きで必要となる場面が出てくるので、あらかじめ多めにコピーをとっておくとよいでしょう。
死亡届の提出
「死亡届」は死亡診断書(死体検案書)とともに渡されます。必要事項を記入し、死亡診断書を添えて「被相続人の死亡地」「被相続人の本籍地のある市町村役場」「届出人の所在地の市町村役場」のいずれかに提出します。
記入する人は被相続人の配偶者や親族などに限られますが、届出をする人は代理人でもかまいません。
また、死亡届もその後の手続きで必要となることがあります。原本は役所に提出してしまうので、コピーを複数枚とっておきましょう。
火葬許可証の取得
「火葬許可申請書」は役所の窓口に置かれています。必要事項を記載して提出すると、引き換えに「火葬許可証」が交付されます。死亡届・死亡診断書の提出と併せて行うとよいでしょう。取得した火葬許可証は、火葬の際に火葬場に提出します。
死亡届・火葬許可申請書の提出は、葬儀社が代行してくれることが多いため、確認してみるとよいでしょう。
遺言書の有無の確認(なるべく)☆
故人の遺言書が残されていないかを調査します。万が一遺産分割協議を終えてから遺言書が見つかると、協議が初めからやり直しとなってしまうケースもあり、大変な手間がかかります。したがって、遺産相続手続きのために最初に行うべきことは、遺言書の有無の確認です。
「自筆証書遺言」の場合、2020年7月から法務局での保管制度が施行されているので、まずは法務局に問合せしてみましょう。そこになかったら、故人が大事なものを保管していそうな場所を探します。自室のどこか、タンスの引き出し、入院していた病院、入所していた施設など心当たりのあるところをあたってみたり、また親族の誰かが預かっていないかということを確認したりしましょう。
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、公証役場で遺言書の有無の確認ができます。こちらもまず問合せしてみましょう。
検認の請求(なるべく)☆
見つかった遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」だった場合、家庭裁判所で「検認」を受ける、という手続きが必要です。
検認とは、家庭裁判所が相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認する手続きで、書き換えなどの不正を防ぐためのものです。検認を受ける前に遺言書を開封することは、たとえ相続人でもしてはいけません。
10日以内に行う手続き
年金の手続き
故人が生前に公的年金を受給していた場合は、それらの受給停止手続きを行います。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内の期限となっているので、期限内に年金事務所窓口への持参または郵送により「年金受給権者死亡届」を提出します。期限を過ぎてしまい、余分に年金を受け取った際には、後日返金しなければなりません。
もし日本年金機構にマイナンバーが登録されていたら、届出の必要はありません。
14日以内に行う手続き
健康保険の手続き
自営業者や学生などは国民健康保険、75歳以上の人であれば後期高齢者医療保険に加入していたはずなので、該当する健康保険に「資格喪失手続き」と「健康保険証の返却」を行います。
その他の健康保険に加入している会社員や公務員であった場合は、ほとんどの場合その勤務先の担当者が退職手続きと併せて資格喪失の手続きを行ってくれます。不安な場合は勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、故人の健康保険の資格喪失届を提出すると、故人の扶養に入っていた家族も同様に資格喪失となります。家族の健康保険証の返却や、新たに国民健康保険に加入するなどの手続きも必要となってきます。
介護保険の手続き
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合は、介護保険の資格喪失手続きも必要です。市区町村役場の介護保険担当窓口に、「介護保険資格喪失届」の提出と、介護保険被保険者証の返却を行いましょう。
手続き後、保険料に未納分があれば相続人に不足分の請求が、納め過ぎがあれば還付金の支払いについての手続き案内が来ます。
世帯主変更届の提出
故人が世帯主だった場合、市町村役場に「世帯主変更届」を提出します。
ただし、残された世帯員が1人である場合や、配偶者と子どものみ、という場合には、次に世帯主となる人は届出をするまでもなく明白であるため、変更届の提出は不要となります。
住民票に関しては、死亡届の提出手続きの際に抹消されるため、抹消届は必要ありません。
金融機関の口座凍結の手続き(なるべく)☆
故人の金融機関の預貯金口座は、死亡届を出したからといって自動的に凍結されるものではなく、基本的に相続人や遺族から連絡をしない限りはそのままです。しかし、そのままにしておくと一部の相続人による使い込みなどの恐れがないとはいえません。
したがって口座の凍結はなるべく早めがよいといえますが、公共料金などの引落口座として使っていた場合、凍結してしまうと未納が発生する可能性もあります。よいタイミングを考えて手続きを行いましょう。
ちなみに、これは10か月以内に行う手続きの項目にある「相続財産の名義変更や換金」とは異なるものなので、注意してください。預貯金の名義変更や換金は、遺産分割協議が終わってから行うものです。
公共料金などの解約・名義変更(なるべく)☆
故人の自宅の電気・ガス・水道・インターネットプロバイダなどの料金は、すぐに家を引き払うのであれば解約の手続きを、片付けや掃除などでしばらく維持したい、その家に家族が住み続けるという場合には料金引落の口座名義変更などの手続きを、早めに行っておきましょう。
故人の口座を先に凍結してしまうと、未納分の督促が来てしまいその手続きにも追われてしまうことになるので、特に期限はありませんが早めに行うことをおすすめします。
クレジットカードやインターネットの有料サイトなどの会員登録、携帯電話なども早期に解約の連絡を入れます。日が経つとその分の会費や基本料金がどんどん請求されてしまいます。
また、免許証やパスポートの返納も行っておきましょう。
1ヶ月以内に行う手続き
雇用保険の手続き
故人が雇用保険を受給していた場合は、「雇用保険受給資格者証」をハローワークに返却します。
遺産相続人の調査・確定・戸籍謄本などの取得(なるべく)☆
遺産分割協議を行うためには、まず法定相続人が何人いて誰なのかということをはっきりさせなければなりません。きちんとした調査を行わないと、遺産分割協議が完了したあとに万が一「他にも法定相続人がいた」というような事態が起きた場合、もう一度協議のやり直しとなってしまいます。
法定相続人の確定のためには、故人の戸籍謄本を集めることが必要です。「故人の出生から死亡までの連続した戸籍」「(子どもがいない場合)故人の両親の出生から死亡までの戸籍」「相続人全員の現在戸籍」を取得します。
注意ポイントとしては、死亡が記載された戸籍謄本だけではなく、「出生から逝去までの連続したすべての戸籍謄本」が必要だという点です。相続人が知らなかった婚姻歴や養子縁組、非嫡出子の存在などを調査し、認識していなかった法定相続人にあたる人物を特定するためです。
戸籍謄本は、結婚や転籍、法改正などで3通以上ある人がほとんどであり、場合によってはこの戸籍謄本取得のステップで非常に時間がかかるため、早めに行動に移りましょう。
相続財産の調査・確定(なるべく)☆
相続財産の内訳を調査していくことも、なるべく早くから進めていきましょう。あとになってから「多額の借金があった」などということが発覚すると、遺産分割協議を何度もやり直したり、相続放棄を考えても期限内に手続きが間に合わなかったり、ということが起こり得るからです。
財産調査のステップでは、さらに細かい過程に分けられます。順番に、漏れなく綿密に進めていきましょう。
①プラス・マイナス両方の相続財産の種類を把握する
プラスの財産として挙げられるものは、
・現金や預貯金
・不動産
・借地権など不動産上の権利
・自動車や貴金属などの動産
・株式や国債などの有価証券、その他の証券
・被相続人が受取人となっている生命保険金
などです。
マイナスの財産として挙げられるものは、
・借金やローンなどの負債
・連帯保証などの保証債務
・未納の税金など
・その他の未払金
などです。
相続財産には含まれないものは、
・墓地・仏壇・遺骨などの祭祀財産
・香典や葬儀費用、埋葬料
・被相続人以外が受取人となっている生命保険金
などです。
②相続財産の資料を調査する
上記の財産項目をもとに、その内容が把握できる資料を集めましょう。故人が大事なものを保管していた場所や、貸金庫などを探してみます。
資料となるものは、たとえば、
・預貯金通帳
・不動産の権利証や登記簿謄本
・不動産の売買契約書
・不動産の納税通知書
・借用書や請求書
・金融機関や証券会社等からの郵便物
・確定申告書の控え
などが挙げられます。
財産内容が複雑で調査が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼することも検討するとよいでしょう。
3ヶ月以内に行う手続き
相続放棄や限定承認の申述☆
遺産相続が発生する際、相続放棄(一切の財産相続の権利を放棄する)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)を検討しているのであれば、家庭裁判所にその旨を申述します。
限定承認の場合は、相続人全員の合意が必要となるため、早めの行動と決断が重要です。
4ヶ月以内に行う手続き
所得税の準確定申告☆
故人の財産について確定申告が必要な場合は、相続人が故人の代わりに確定申告を行います。これを準確定申告といいます。
以下のような場合は、準確定申告を行わなければなりません。
・故人が自営業や不動産事業を行っていた
・2ヶ所以上から給料をもらっていた
・給与所得が2,000万円を超えていた
・給与や退職金以外の所得があった
などです。
また、医療費の支払いが高額だった場合などでは、還付金をもらえることがあります。このケースでは準確定申告を「しなければいけない」ということはありませんが、「しておいた方がよい」といえます。
遺産分割協議の開始・遺産分割協議書の作成(なるべく)☆
遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産をどう分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行い、協議書として作成する必要があります。
遺産分割の方法には、現物をそのまま分割する「現物分割」、不動産など現物を分割できない相続財産を売却し、その金額を分割する「換価分割」、不動産などをまるごと相続した人が本来の相続分以上の取得をしていたら、その分の代償金をほかの相続人に分割する「代償分割」、持分を決めてそのまま共有する「共有分割」の4パターンがあります。
協議は必ずしも全員が一か所に集まって話し合いをする必要はなく、電話やメールなどで連絡を取り合いながら協議を進めても問題ありませんが、相続人の人数が多かったり、話し合いで揉める可能性も考えたりすると、こちらも早くから着手を始めるのがよいでしょう。
また、相続税の申告や預貯金の名義変更・口座解約、不動産の相続登記の際には、遺産分割協議書が必要になります。相続税の申告と納付は10か月以内なので、どんなに遅くてもこの期限に間に合うようには協議書を完成させておきましょう。
遺産分割協議書には「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を明確に記載し、相続人全員の署名と捺印が必要になります。
10ヶ月以内に行う手続き
相続税の申告・納付☆
相続財産の分割方法が決まったら、相続財産の評価額全体を計算して、相続税の申告と納付を行います。
ただし、相続税は相続財産があったら必ずかかる、というものではありません。基礎控除額が定められているので、その額に収まる場合は申告も納税も必要がない、ということになります。
基礎控除額の計算式は、以下の通りです。
「相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円」
たとえば、相続人が3人いれば「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」という計算になり、4,800万円が基礎控除額と産出されます。つまり、相続財産の評価額が4,800万円を下回れば、相続税の申告・納付は必要ないということになります。
相続税には、基礎控除の他にもさまざまな控除や特例があるので、相続税の納付は必要がなかったということは意外に多いものでしょう。少しでも節税できるように、いろいろと調べてみることをおすすめします。
相続財産の名義変更や換金(なるべく)☆
遺産分割協議書の作成が完了すれば、ようやく各相続財産の相続手続きを行うことができます。必要書類や手続きの細かい流れは金融機関などによって異なるため、まずは連絡を入れて確認しましょう。
預貯金や有価証券、不動産などの他にも、自動車やゴルフ会員権といったものの相続財産も名義変更手続きを行います。
1年以内に行う手続き
遺留分侵害請求☆
「遺留分」とは、本来その相続人が受け取れるはずの最低限の相続分のことをいいます。
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、配偶者や子どもなどの法定相続人には、遺産を多く受け取った人に対して遺留分を請求できる権利があり、これが「遺留分侵害請求権」です。
たとえば、遺言書に「愛人にすべての財産を遺す」と書かれていたとしましょう。その通りに愛人に全財産を相続させても問題はありませんが、配偶者と子どもがこれに納得できないのであれば、愛人に遺留分にあたる金額を請求することができます。
遺留分侵害請求の期限は、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内であり、相続の開始を知らなかったというケースでは、相続開始から10年以内です。
2年以内に行う手続き
埋葬料請求
故人が健康保険の被保険者だった場合は、5万円の「埋葬料」が請求できます。加入している健康保険組合または協会けんぽに、健康保険埋葬料請求書・健康保険証・死亡診断書(コピー可)・葬儀費用の領収証などを提出します。
葬祭費請求
故人が国民健康保険か後期高齢者医療保険の被保険者だった場合、市区町村へ「葬祭費」の請求ができます。金額は1~7万円で、市区町村によって異なります。
市区町村の役所窓口に、故人の健康保険証・申請者の本人確認書類・印鑑・葬儀費用の領収証などを用意して申請しましょう。
埋葬料・葬祭費の請求は、どちらも2年以内の期限にはなっていますが、健康保険の資格喪失手続きと同時に行ってしまう方が手続きし忘れを防ぐことができるでしょう。
高額医療費の還付請求
故人が亡くなる前に入院や手術などによる高額な治療費の支払いがあった場合には、高額医療費」の還付請求ができます。加入していた健康保険組合・協会けんぽ・市区町村に、医療費の明細などを用意して申請しましょう。
3年以内に行う手続き
相続登記(不動産の名義変更)☆
相続登記とは、相続した不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きのことです。これまで相続登記には期限がありませんでしたが、2024年4月からは義務化され、3年以内という期限が設けられました。こちらは財産の名義変更の際に、一緒に行ってしまうのがよいでしょう。
不動産の管轄法務局に、必要書類を用意して登記を行います。
生命保険金の受取☆
故人が生命保険金に加入していれば、保険会社に連絡をして保険金を受け取る手続きを行いましょう。保険会社によって必要書類などは異なるため、保険証券などを手元に用意し、まず手続き方法の確認を行います。
生命保険は、残された家族の当面の生活費などに充てられるよう準備されていることが多いものなので、請求期限は3年以内といえども、できるだけ早めに受け取る手続きを行うべきでしょう。自動で支払われるわけではないので、自分で請求手続きを行わなければなりません。
ちなみに、生命保険は受取人が故人名義になっていると、相続財産に含まれます。
5年以内に行う手続き
遺族年金の請求
国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族年金を受け取れる可能性があります。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、家族構成や収入によって受給できるかどうかが決まるため、まずは年金事務所に確認してみましょう。
手続きの期限は5年以内と長いですが、遺族年金は遺族の生活費の大きな助けとなるものであるため、生命保険などと同様にできるだけ早くに手続きを行うのが最善です。
故人の未支給年金の請求
年金は、たとえば「2月と3月の2か月分は4月に支給される」というように、支給前月までの2か月分を受け取る仕組みになっているため、受け取れるはずの年金が死亡することによって支給されていない、ということが発生します。亡くなった月までの年金は、故人と生計を一としていた遺族が受け取れるので、厚生年金は年金事務所へ、国民年金は住所地役場の年金窓口へ、「未収支給年金請求書」の提出をします。
請求期限は5年以内ではありますが、年金受給停止手続きと同時に行ってしまえば、手続きのし忘れを防げるでしょう。
まとめ
遺産相続の手続きのみならず、人が亡くなると本当に多様な手続きが必要だということがわかります。手続き先も一か所に集中しているわけではないので、効率的に進めるにはやはりあらかじめ知識を持っていることが大事です。
全体で見たら膨大でも、ひとつひとつを期限内に行っていけばそれほど大変ではなくなります。相続人同士で協力して、余裕をもって遺産相続の手続きを進めていきましょう。