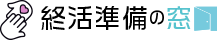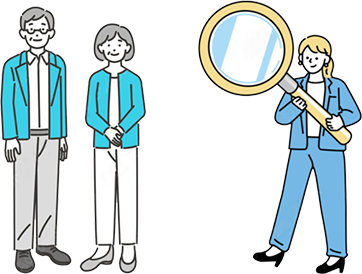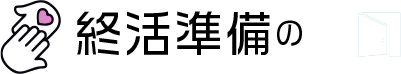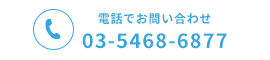人がひとり亡くなると、さまざまな手続きややるべきことが生じます。それらを全部まとめて「死後事務」といい、通常は故人の家族や親族が行うものですが、何らかの事情でそれが無理である場合、生前のうちから第三者に委任する契約を結んでおくことができます。
今回は死後事務の具体的な内容、また委任契約を結ぶ際の流れなどを解説します。
死後事務委任契約の概要
死後事務とは
人が亡くなったあとには、さまざまな事務処理がつきものです。死亡届の提出や年金受給の停止などの行政手続き、葬式や埋葬の手配、医療施設や介護施設の費用の精算、遺品整理など内容は多岐に渡り、時間も手間もかかるものです。
死後事務と呼ばれるものの一般的な内容の詳細は、後ほど詳しく解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、前述した「死後事務」を、自分の死後に第三者に行ってもらえるように生前のうちに交わす契約です。死後事務の一部でも、全部でも、契約当事者同士が合意する範囲での契約となるので、必要かつ十分な内容で委任することができます。
委任する相手にも制限はなく、友人や知人のような第三者でも、弁護士などの法律家でもかまいません。
有償・無償なのかどうかも、契約当事者同士の合意さえあれば自由です。ただ、確実に執行してほしい、事情が込み入っていて死後事務に複雑な要素が絡む、などのケースでは、きちんと有償で法律家と契約を交わすのが最善といえるでしょう。
死後事務委任契約を行うべき人
通常、死後事務は亡くなった人の家族や親族などが行いますが、さまざまな事情で身内に頼めないという人もいることでしょう。たとえば、以下のような人が挙げられます。
〇一人暮らしで身寄りがいない
〇家族が高齢である
〇親族が遠方に住んでいる
〇家族・親族はいるが、迷惑や負担をかけたくない
〇親族との折り合いが悪く、連絡も取れない
〇具体的に希望するお葬式形態や埋葬方法がある
〇内縁関係の相手がいる
など。
このような人たちにとって死後事務委任契約の存在は頼りになるものですが、もちろん家族がいる人でも委任契約を交わすことは可能です。その場合は、あらかじめ「第三者に死後事務をまかせる契約を交わした」ということを家族に伝えておかなければ、トラブルにつながりかねないため、注意が必要です。
死後事務委任契約を結べる人
前述したように、死後事務委任契約を結べる相手には制限がなく、弁護士・行政書士・司法書士などの法律家や、友人・知人、また内縁関係の相手などでもかまいません。
ただし、「契約などの法律行為ができない人(認知症の高齢者など)」は当然受任者にはなれません。
死後事務委任契約を結ぶメリット
最大のメリットは、自分の死後に対する不安をなくせるという点です。家族や親族に迷惑や負担をかけるのではないか、手続きを行ってくれる人がいないために無縁仏になってしまうのではないか、死後に必要な手続きに漏れが生じないか、自分の希望通りの葬儀・埋葬をしてもらえるか…こういった不安を解消することで、安心して終活を進め、身辺整理を行っていくことができるでしょう。
死後事務の内容
死後事務にはさまざまなものがありますが、必ず行わなくてはいけないものばかりではありません。したがって、自分にとって必要な内容、希望する事項を具体的に挙げておく必要があります。死後事務委任契約で託せる内容には、主に以下のようなものがあります。
死亡に伴う事務
〇遺体の引き取り
〇遺族への連絡
〇指定された形態での通夜・葬儀・告別式の手続きや執行
〇指定された形態での火葬・納骨・埋葬の手続きや執行
など。
現在、さまざまな事情で遺体の引取人がいない高齢者は増加の一途をたどっているといわれています。孤独死・無縁仏となった場合は自治体が火葬後、合葬墓に埋葬されることになりますが、その際の自治体や賃貸物件の貸主にかかる負担は社会問題化しているほどであり、それを防ぐためにも死後事務委任は重要な役割を果たすのです。
行政手続きに関する事務
〇死亡届の提出
〇健康保険証・介護保険証・運転免許証などの返還
〇年金の受給停止手続き
〇固定資産税などの未払い分清算
など。
未払い分などの債務は、本来相続人が引き継ぐことになるため、最終的に相続トラブルにつながる恐れもあります。相続人である親族などに督促が行く前にきちんと清算できるよう、受任者には預託金を用意しておき、滞りなく支払いを行ってもらいます。
住まいや生活に関する事務
〇医療費・介護施設費の清算
〇家賃・光熱費などの未払い分清算
〇自宅の清掃・遺品整理・家財処分
〇賃貸物件の解約や明け渡し手続き
〇クレジットカードなど各種契約の解約手続き
〇サブスクリプションサービス・会員サービスなどの解約手続き
〇SNSなどのアカウント削除
〇パソコンや携帯電話のデータ抹消処理
〇残されたペットの引継ぎ手続き
などなど。
住まいや生活に関することには、個人情報が多く含まれています。パソコン・携帯電話のロックの解除やアカウントの削除にはパスワードが必要であり、デジタル遺品の整理もデリケートな作業です。生前のうちにこれらの作業に必要な情報をまとめておき、死後事務委任の際には受任者にきちんと伝わるよう手配をしておかなければなりません。
死後事務委任契約と他の制度との関係性や違い
終活において利用できる制度はいくつかあり、死後事務委任契約の内容と相互に抵触してしまうものや、併用することで効果を発揮できるものについて知っておかなければなりません。
死後事務委任契約と遺言書の関係
遺産相続についての希望や手続きは、死後事務委任契約では法的拘束力がなく、依頼できません。財産・相続・相続人に関わる意思表示には「遺言書」が必要となります。
言い換えれば、遺言書では財産関係と身分(非嫡出子を認知したいなど)についての内容しか希望を叶えることができません。つまり死後事務委任契約と遺言書では、それぞれにできることとできないことがあるため、両者を併せて利用することで、死後の希望をすべて実現させられるのです。
死後事務委任契約と財産管理委任契約・成年後見制度の関係
死後事務委任契約は、その名の通り「死後に発生する手続き」を委任するものであるため、生前のことは依頼できません。たとえば、生前の財産管理や行政手続きなど(身上監護)といったものです。
これを叶えるには「財産管理委任契約」や「成年後見制度」の利用が考えられます。
どちらも生前の財産管理を委任できるものですが、成年後見制度は「精神上の障害により判断能力が不十分だと判断された場合」にしか利用できないという違いがあります。判断能力に関わらず生前の財産管理をまかせたい場合は財産管理委任契約を選ぶとよいでしょう。
ただ、財産管理委任契約には「公正証書の作成や後見登記が行われないため社会的信用が不十分」「監督者がいないため実際に契約した内容が行われているか確認不可能」という弱点があります。
生前・死後の両方で財産管理を委任したい際には、死後事務委任契約と、財産管理委任契約もしくは成年後見制度との併用が最善といえども、この両者の間にもメリット・デメリットがあるので、十分な検討が必要となるでしょう。
死後事務委任契約締結の流れ
死後事務委任を決めたら、契約締結のタイミングは「心身ともに健康であるうち」がベストです。突然認知症を発症するという可能性も考えると、判断能力がしっかりしている間に契約を考えるのがよいといえます。
1 誰に委任するかを決める
前述したように、友人や知人に委任するのか、法律家や業者に依頼するのかということを決めます。契約自体に不安がある方は、やはり法律家に相談しながら進めていくことも考えましょう。
2 委任内容を固める
自分に必要な内容、希望する項目をしっかり書き出して固めます。不要なものまで盛り込む必要はないので、納得いく内容になるまで絞り込みましょう。
依頼したい内容はもちろんのこと、たとえば葬儀や埋葬に関してはその形式や規模など、具体的な指定まで行い、またアカウントの削除やデジタルデータに関する作業にはパスワードの確認方法などもきちんと残せるようにしておきます。
3 必要なものをそろえる
死後事務委任契約は、委任者と受任者双方の合意があれば、口頭でも契約は締結できます。しかしどんな契約でも同様ですが、のちのちのトラブル防止のために契約書は必ず作成しておくべきといえます。
契約書は、委任先が法律家や業者であれば公正証書化しておくことが一般的なので、そのために必要なものを用意しておきましょう。
用意するものは、次のいずれかの組み合わせです。〇実印+印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)〇認印+自動車運転免許証〇認印+顔写真付きのマイナンバーカード〇認印+顔写真付きの住民基本台帳カード委任者と受任者のそれぞれが用意します。
4 契約書を作成して公正証書化する
「公正証書」とは、公証人が作成し内容を証明する公文書で、証明力と執行力を持つ文書です。死後事務は本人が亡くなってから執行するものなので、契約書は公正証書化することで、より安全で確実性の高いものになるといえます。
5 委任者の死後に受託者が委任内容を執行する
契約書の内容に沿って、受任者が滞りなく死後事務を執行します。
6 相続人に報告・清算する
死後事務の依頼内容がすべて終了したことを相続人や相続財産管理人に報告し、もし預託金に余剰分があればそれを返還、万が一足りない分があればその清算を行います。
死後事務委任契約にかかる費用
費用内訳
死後事務委任契約に必要な費用は、当然ながら「どこまでを依頼するか」でかなりの幅が出ます。また、「誰に依頼するか」ということでも金額に差が開きます。友人や知人に無償でお願いできることもありますし、委任が必ず執行されるように法律家や専門業者に依頼すれば、相応の報酬を用意しなければなりません。
ここでは、大体の費用相場を見ておきましょう。
死後事務委任契約書の作成料
きちんとした契約として残すためには、契約書の作成が必要となります。専門家に依頼する場合は、30万円前後見ておきましょう。
公証役場で作成した場合は、手数料1万1千円の支払いが必要です。
死後事務執行の報酬
死後事務全般をお願いする「報酬」は、誰にどこまでの内容を依頼するかで費用にかなりの差が出ます。50万~150万円ほど見ておきましょう。
死後事務にかかる実費
死後事務の手続きの際に発生する費用を見積もっておいて、受任者にあらかじめ預けておく「預託金」というものです。すぐに必要になる費用を前もって渡しておけば、受任者が立て替えて支払うなどの煩雑さがなくなるため、まとまった金額を用意しておきます。
こちらも、依頼する死後事務の内容で金額が大きく変わります。特に葬式費用や医療費・介護施設費の清算までお願いする場合は、高額になることが予想されるはずです。
費用支払い方法
死後事務委任契約の費用支払い方法には、いくつかのパターンがあります。注意したいのは、「先に高額の支払いがある」「遺産がなければならない」「生命保険の契約が必要」などの条件があり、それに合わなければ費用の支払いができず、したがって死後事務委任契約を結ぶこともできません。自分の資産状況にきちんと合った契約相手を探すことも重要です。
預託金で清算する
預託金とは、生前に前もって死後事務受任者に預けておく金銭です。委任者の死後、受任者はその預託金を使って委任されていた内容を執行します。
メリットは、最初に必要な費用と報酬を預けておくことで、支払いに関する件で揉める恐れが少なくなることでしょう。もし契約を解除したとしても、しかるべき金額はきちんと戻ってきます。
デメリットは、生前に高額な費用が必要となる点です。知人などに委任するのではなく法律家と有償で契約する場合は、それなりの報酬が発生するため、先にそれを用意しておくには資産に余裕を持っておく必要があります。
また、信用度の高くない相手に委任してしまうと、預託金を使い込まれてしまう可能性も考えられます。これを防ぐには、信託銀行に口座開設をして、そこに預託金を入れておくという方法があります。こうすれば死後事務以外で預託金を使うことはできなくなります。
遺産で清算する
亡くなったのちに、遺産から必要費用と報酬を清算する方法です。遺産の相続内容に触れることになるため、遺言書でこの旨を書き残す必要があります。
メリットは、預託金方式と違って先にまとまった金銭を用意しなくてもよい点です。死後事務はその名の通り死後に行われるものなので、生前の内から一括で必要費用と報酬を支払っておくことに抵抗がある方にとっては、よい方式といえるでしょう。
デメリットは、前述した通り「必ず遺言書とセットにして考えなければいけない」という点です。したがって、遺言書を書くつもりがない、書きたくないという方には向いていないといえるでしょう。
また、遺産の金額が万が一死後事務執行に必要な分を満たしていないと、死後事務は行ってもらえない可能性があるため、遺産の管理にも気を配らなければなりません。
保険金で清算する
契約を結んでいる生命保険会社からの保険金で、必要な費用と報酬を清算する方法です。受任者が死亡保険の受取人になれる少額短期保険を利用することが多くなっています。
注意点は、保険に入る際に審査があることです。審査に通らなければ加入できないため、この方法をとることは不可能となります。
死後事務委任契約を結ぶ際の注意点
家族や親族に契約のことを話しておく
一般的に死後事務は、家族や親族など身内が行うと認識されているものです。もし第三者に死後事務委任を考えているのであれば、あらかじめその旨を家族や親族に伝えておくのがよいでしょう。
亡くなってから第三者に委任されていることが発覚すると、たとえ委任者が家族の迷惑や負担を取り除く目的で契約を結んでいたとしても、何らかのトラブルにつながったり、受任者に不信感を抱いたりなどの遺恨が生じたりする恐れがあるからです。
また、委任の内容に関してもできる限り家族・親族には伝えておき、意向を理解してもらっておくのが最善です。
必要費用・報酬の支払いに関して十分確認しておく
特に法律家や業者などに預託金を預けて契約を結ぶ場合は、その預託金の扱い(信託銀行などに預けるのか、解約時にはどのような規定になっているのかなど)に関してしっかりと確認しておくことが重要です。
業者などと死後事務委任契約を結ぶケースでは、預託金での支払い方式がもっとも多いといわれています。受任者が死後事務を滞りなく進めるためには、預託金の存在が不可欠であるとはいえ、やはり大金を前もって預けることには不安が伴うものでしょう。
自分の死後のことであれば、それはなおさらです。納得がいくまで疑問点を解消し、契約締結に至るようにしたいところです。
受任者にもしものことがあったケースに留意する
業者などではなく、友人や知人など個人に死後事務を委任すると、万が一委任者よりも先に受任者が亡くなった場合には、その時点で契約が消滅してしまいます。稀なケースだからと油断はせず、そのような想定外の事態が起きたときにはどうしていけばいいのかということも、しっかり考えておきましょう。
まとめ
自分が亡くなったあと、残された人たちが行うべきことはずいぶん多いものだと感じられたのではないでしょうか。してもらうのが当然だとは思わず、生前のうちから準備しておこうというときに、死後事務委任契約という存在は非常に頼りになります。
注意点は多く、かかる費用は相応のものですが、必要に応じて有効に活用していきましょう。