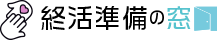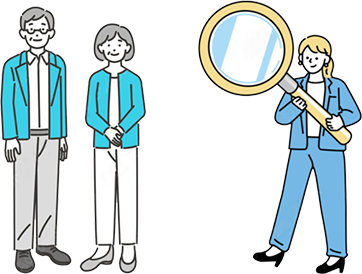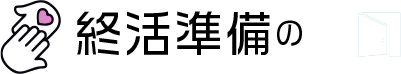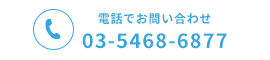少子高齢化社会の加速に伴い、高齢者への支援制度は近年どんどん充実してきています。「任意後見制度」もそのひとつで、もともとあった「成年後見制度」のなかに「法定後見制度」と並ぶ位置づけで平成12年に整備されました。
任意後見制度には、法定後見制度にはないメリットがあり、さらに高齢者の希望に沿うことができる仕組みになっています。一方で、デメリットや利用にあたっての注意点もあるため、その他制度との違いなども併せて知っておくことが重要です。
※本記事では「本人」「被後見人」「後見対象者」はすべて同じ意味で使用しており、「後見される人」を指しています。
※「任意後見受任者」とは、任意後見が開始される前の状態の「任意後見人」を表す語です。
任意後見制度の概要
そもそも「後見人」とは?
後見制度で選任される「後見人」は、「成年後見人」という呼び方もされるもので、「背後に控えて世話をし、面倒を見る人」という意味があります。具体的には生活・医療・介護などの面で本人を保護・支援する役割(身上監護)を持ち、また財産の管理も行います。
「任意後見制度」と「法定後見制度」の関係
任意後見制度と法定後見制度は、どちらも「成年後見制度」というものです。言い換えると「成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度のふたつの形態がある」ということになります。
両方とも、判断能力を失った人の財産を管理するための制度ですが、大きな違いのひとつとして、任意後見制度は「将来後見人となる人をあらかじめ自分で決めておくことができる」という特徴があります。つまり、判断能力を失う前に、失ったあとに備えて後見人を選んでおけるのです。
これに対して法定後見制度は、本人が判断能力を失ってしまったあとに、家族などの後押しにより家庭裁判所が後見人を選ぶものです。すでに判断能力がないため、本人自身が後見人の指定はできません。弁護士など家族以外の人が選任されることもあるので、それを不安に思う人も少なくないといえます。
したがって、認知症対策などとして後見制度を考えるのであれば、法定後見制度ではなく任意後見制度を選んでおくのがよいのです。
任意後見制度の3つの形態
任意後見制度には、後見人が役割を果たす時期において、3種類のタイプがあります。
1:即効型契約
任意後見制度の契約と同時に、後見が開始するタイプです。
判断能力の低下が軽度の場合は任意後見制度が利用できるため、本人がまだ契約締結できる程度の意思能力を有している場合に有効な契約です。したがって、軽い認知症をかかえている人が将来のことを案じ、判断能力のあるうちにのちのち財産管理をしてくれる後見人を決める場合に使われることが多くなっています。
すぐに後見が開始されるため、判断能力のある本人と後見人との間できちんとした意思疎通を必要とします。
ただし、任意後見契約は契約内容を理解するだけの判断能力は必要であるため、契約締結時に判断能力がすでに不十分であると判断されると、場合によっては契約自体が無効になってしまう恐れがあることには注意しておきましょう。
2:将来型契約
事前に後見契約を結んでおき、判断能力が低下したら後見が開始するタイプです。
判断能力があるうちに信頼できる後見人を選んでおき、判断能力が低下し始めたらすぐに後見が開始するため、安心な制度です。ただし、判断能力が低下してきていることを後見人が判断できない環境にいる(離れて暮らしているなど)場合は、注意が必要です。
3:移行型契約
段階を踏んで後見に移行していくタイプです。任意後見制度ではもっとも多く用いられる方法です。
この場合、財産管理委任契約などと任意後見契約の2つを結び、判断能力の程度に合わせて各々の契約に沿い、後見を行います。判断能力の低下具合に応じて適切な後見ができるというメリットがあります。
任意後見人になれる人・なれない人
基本的に、任意後見人には本人が信頼する人であれば誰でもなることができます。家族や親族のほかにも、友人や弁護士などの法律家のような第三者でも可能です。
ただし、明確に「任意後見人になれない人」は定められています。
〇未成年者
〇過去に家庭裁判所に解任された補助人
〇同上の保佐人
〇同上の法定代理人
〇破産者
〇行方の知れない人
〇本人に対して訴訟をした人、またはその配偶者や直系血族
〇不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見人の任務に適しない事由がある人
などは、任意後見人にはなれません。
後見人の仕事
任意後見人が行う仕事は、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つがあります。
財産管理
一言でいうと「金銭が絡むことの管理」です。
本人の銀行口座の預貯金の管理や不動産などの売却、契約行為などを指します。あくまで「維持管理」が目的であるため「運用」はできません。
後述しますが、任意後見人制度では、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」という存在があり、監督人が後見人の仕事を監視する役目を持つため、財産の不正な管理などを抑止する体制である点にも安心できます。後見人は、監督人に財産の管理状況を報告する義務を持ちます。
身上監護
身上監護とは「本人の生活を維持し、医療や介護に関する法律行為」のことです。
住居の確保や介護施設の入所契約、入院の手続きや医療費の支払いなどが該当します。
任意後見人の仕事に含まれない行為とは
たとえば介護行為そのものや、ペットの世話などは任意後見人の仕事には含まれません。ただ、家族が任意後見人となる場合は、こういった行為を「後見人として」ではなく「家族として」行うことは可能です。
任意後見人の報酬
法律上では、任意後見人に対する報酬は定められておらず、特約がない限りは無報酬です。また報酬の支払い時期についても、規定がなければ任意後見契約終了後(つまり本人死亡後)となります。
したがって、報酬を支払うためには、また定期的に報酬の支払いを行うためには、任意後見契約書作成の際に報酬についての規定を特約として盛り込んでおく必要があります。
特約として記載するのであれば、報酬額や支払い方法、支払い時期などは本人と任意後見受任者との間で合意によって、自由に決めることが可能です。
報酬の相場は、管理財産額によっても変動しますが、相場としては月額5,000~60,000円程度です。また、身上監護などで特別困難な事情があった場合には、基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬がプラスされます。
任意後見契約が終了するとき
契約終了の要件
任意後見契約は、以下の場合に終了します。
〇本人または任意後見人が死亡・破産した場合
〇任意後見人が認知症などになった場合
また以下の場合は、任意後見監督人・本人・本人の親族・検察官が解任請求することにより、家庭裁判所が任意後見人を解任することができます。
〇任意後見人に不正行為や著しい不行跡があった場合、またその他の任務に適しない事由があった場合
さらに、本人または任意後見人が申立てすることにより、契約の解除(任意後見人の辞任)も可能です。
契約解除の要件
〇任意後見監督人の選任前…いつでも契約解除可能、ただし公証人の承認が必要
〇任意後見監督人の選任後…正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て契約解除可能
契約内容の変更
任意後見契約の内容をあとから変更することは可能です。ただし、代理権に関する内容は変更ができないため、新たに契約を結び直すことになります。
いずれにしろ、変更内容は必ず公正証書で残します。
任意後見監督人とは
先に少し触れましたが、任意後見契約の際には家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。
「この人に後見監督人になってほしい」という希望は、公正証書に記しておくこと自体は可能ですが、希望通りにその人物が監督人に選任されるとは限りません。あくまで家庭裁判所が選任するものであり、その決定に従う必要があります。
任意後見監督人の仕事
任意後見人の業務監督
任意後見人が被後見人の財産管理をするにあたり、不正行為がないか、適切な行動をとっているかということを、家庭裁判所が逐一監視することは不可能です。
そこで任意後見監督人が、家庭裁判所と連携しながらこれらのことを定期的にチェックします。後見人は監督人に、財産管理についての報告をしなければならず、財産管理に不備があった場合は、監督人は家庭裁判所に報告してしかるべき措置をとる役割も担っています。
任意後見対象者の代理行為
後見人が利益相反行為にあたる行動を取るような状況下では、監督人が後見対象者の代理を務めることがあります。
たとえば、後見対象者と後見人が同じ家族であり、そこで相続が発生したケースが考えられます。このような場合、後見人の利益相反行為にあたる相続手続きが発生する可能性があるため、監督人が後見対象者の代理として相続手続きに関わることがあるのです。
緊急事態における任意後見人の代理行為
任意後見人に万が一のことがあり、急に後見人としての職務ができなくなってしまうような緊急事態には、一時的に任意後見監督人が後見人の代理としてその職務を引き継ぐことがあります。
任意後見監督人の報酬
任意後見監督人は、その業務の性質上、弁護士や司法書士など専門的な知識や経験を持つ人物が選任されることが多いため、監督人にも報酬が発生します。もちろんこの報酬も被後見人の財産からの支払いとなります。
報酬額は家庭裁判所が決定しますが、管理対象となる財産の額によっての目安が存在します。
〇管理財産額が5,000万円以下の場合…月額10,000~20,000円
〇管理財産額が5,000万円を超える場合…月額25,000~30,000円
任意後見制度を積極的に利用すべきケースとは
任意後見人を特定の人物に指定したいとき
先にも述べたように、任意後見制度は、誰が後見人になるかわからない法定後見制度と違って、任意後見対象者がみずから後見人を選ぶことができます。
そのため、この人に後見人をお願いしたい、という特定の人物がいる場合は、任意後見制度を利用すべきといえます。
「信頼できる家族や友人に後見人になってほしい」、それとは逆に「弁護士などの専門家に依頼できれば安心」など、確実に特定の人物に後見を依頼したいのであれば、法定後見制度ではなく任意後見制度が適しているでしょう。
障がいのある子どもの後見人に親がなりたい場合
障がいを持つ子どもが未成年の間に任意後見制度を利用し、親が後見人なっておくことで、子どもが成人したあとも親が引き続き財産管理や生活のサポートができるようになります。
任意後見制度を利用しない場合、成人後は法定後見人が選任され、親が直接財産を管理することが難しくなるため、未成年の内から任意後見制度の利用を検討するとよいでしょう。
任意後見人のメリット
後見人を自分で選べる
前述したように、任意後見制度では後見人を自分で自由に選ぶことができます。判断能力がしっかりしているうちに、自分の信頼できる人を後見人として立てられるため、いざというときにも安心できるでしょう。
後見人の権限内容を自由に決められる
任意後見人は判断能力がしっかりしているうちに選べるので、後見人にまかせたい内容も本人の希望通りに決められます。お願いしたいこと、不要なことを明確に伝えておけるので、これも安心につながるメリットといえます。
任意後見監督人のチェックがある
先にも述べた通り、任意後見制度には「任意後見監督人」という存在があり、任意後見人の権限濫用などの不正を監視してくれます。判断能力が低下したあとも、安心して後見制度を利用できる一助となるでしょう。
任意後見人のデメリット
後見人に「取消権」がない
取消権とは、本人が自分に不利益な契約などを結んでしまった際に、それを取り消す権利のことです。法定後見人はこの取消権を持ちますが、任意後見人には認められていません。
したがって、本人が判断能力を欠いた状態でたとえば詐欺の契約にあったとしても、任意後見人がそれを取り消せないのです。
「財産の保護」も任意後見人の役割のひとつであるため、取消権が認められていないことに関しては、重々注意しておく必要があるといえます。
契約を一方的に解除される恐れがある
任意後見契約は、締結の際にはお互いの合意があって可能となりますが、解除は後見人から一方的にできてしまうという難点があります。
将来に備えて任意後見人を選んだのに、契約を解除されてしまって、また別の人と契約の結び直し…ということもありえる点に注意が必要となります。
任意後見制度を利用するための手続きの流れ
1:後見人と後見内容を決める
信頼できる後見人の候補を挙げ、了承が得られたら後見の依頼内容を決めます。契約方法についても、前述した3種類から選びましょう。
後見人は、財産管理をメインに依頼したいのであれば弁護士などの専門家を、身のまわりの生活支援をメインにしたいのであれば親族や友人を、というように自分の希望に合わせて選んでもよいでしょう。
依頼内容として具体的に決めておきたいものは、
〇日常生活の支援・医療や介護の方針や支援内容
〇現金や不動産などの財産の管理方法・権限
〇法的な代理行為の範囲
〇後見人の報酬額と受取方法
などです。
2:契約書を作成する
後見内容をはじめとして、さまざまな取り決めをきちんと書面に残しておくために、任意後見契約書を作成します。
後見人を専門家に依頼する場合は、そのまま専門家に契約書作成もお願いすることになるので、間違いがありません。親族など身近な人に依頼する場合も、契約書は公正証書での作成が必要となるため、公証役場で手続きを行います。
内容が複雑な場合は、契約書の案作成だけでも専門家にお願いすることができます。
〇任意後見契約書作成時の必要書類
・任意後見契約の契約書案
・被後見人の戸籍謄本または住民票
・被後見人の印鑑証明書と実印
・被後見人の身分証明書
・任意後見受任者の住民票(法人の場合はその登記簿謄本)
・任意後見受任者の印鑑証明書と実印
・任意後見受任者の身分証明書
・その他、被後見人の財産目録や診断書など、公証役場に要確認
※各書類は発行から3ヶ月以内のもの
〇任意後見契約書を公正証書として作成する際の費用
・公証役場の手数料…11,000円
・法務局への登記嘱託手数料…1,400円
・印紙代…2,600円
・書留郵便料…540円
・正本謄本の作成手数料…1枚250円
・専門家への支払報酬:10万円前後(手続きを弁護士や司法書士などに依頼する場合)
など
3:公証人が家庭裁判所へ登記依頼を行う
公証役場で任意後見契約が成立すると、公証人が法務局に登記依頼を行います。2~3週間で登記が完了して、登記事項証明書に任意後見人であることが記載されるようになるので、最寄りの法務局で取得します。以後は後見人である証明として使うことができます。
4:家庭裁判所への申立をする
本人に判断能力の低下が見られ、任意後見開始の時期となったら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行います。この申立は、本人・配偶者・任意後見受任者・本人の四親等以内の親族・法定代理人が可能です。
〇任意後見監督人選任の申立に必要な書類
・任意後見監督人選任申立書
・被後見人の事情説明書
・診断書
・任意後見受任者の事情説明書
・親族関係図
・収支状況報告書
・財産目録
・任意後見契約公正証書の写し
・被後見人の戸籍謄本
・被後見人の住民票
・後見登記事項証明書
・被後見人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
・任意後見受任者の住民票
など
〇任意後見監督人選任の申立に必要な費用
・申立手数料…800円
・登記手数料…1,400円
・郵便切手代…3,000~5,000円程度
・精神鑑定費用…5~10万円程度(鑑定が必要な場合のみ)
申立が行われると、家庭裁判所が申立人および任意後見受任者と直接面接を行います。その後家庭裁判所において被後見人の調査と、必要があれば精神鑑定が行われます。
5:任意後見監督人選任完了、任意後見開始
任意後見監督人が選任されると、その旨が任意後見人に郵送で通知され、任意後見が開始となります。
任意後見制度と比較、もしくは併用したい制度
任意後見制度と、法定後見制度・家族信託の違い
法定後見制度
前述した通り、任意後見制度は本人にまだ判断能力があるうちに、将来的に判断能力を失ったときに備えて、自分で後見人を選べる制度です(ただし前述したように、家庭裁判所が後見人を監視する任意後見監督人を選任します)。
対して法定後見制度は、判断能力を失ってから初めて家庭裁判所に申立を行います。本人が申し立てることは不可能な状態なので、親族などが代わりに申立をします。後見人は家庭裁判所が選任するため、これまで関わりのなかった弁護士が後見人となる、などということも起きる点に、信頼できるのかどうかと不安を感じるデメリットがあります。
また、任意後見制度では後見の内容や権限を契約によって柔軟に決められますが、法定後見制度は民法および家庭裁判所の審判によって、権限内容が決定されます。
さらに後見人は本人の財産の動きを定期的に報告する義務、財産を処分する際には裁判所の許可を得る義務を負います。
加えて、法定後見制度の終了は原則として後見対象者の判断能力が戻ったときと死亡したときのみであり、途中でやめることはできません。
家族信託
家族信託と任意後見制度の共通点は「本人の判断能力があるうちに契約しなければならない」という点と「委託者が希望する人物に信託できる」という点です。
異なる点は、後見人と違って「財産の管理など」しか認められておらず、法律行為の代理は不可能だという点です。
法定後見制度とも違って、委託者と受託者の両者合意があれば、また終了事由をあらかじめ取り決めておけば、途中で終了することも可能となっています。
任意後見制度と併用を検討したい制度
死後事務委任契約
任意後見人制度は、本人が死亡した時点で契約が解除されてしまいます。
そのため、葬式の準備やさまざまな行政手続きなどの、いわゆる「死後事務」まで後見人に依頼したい場合には、任意後見契約とともに死後事務委任契約も結んでおく必要があります。任意後見制度ではカバーできない部分を、死後事務委任契約が補うという見方をすればわかりやすいでしょう。
生前と死後で、支援してもらうための契約は別で存在しているということを理解しておき、使い分けや併用を検討しなければならない、といえるでしょう。
見守り契約
任意後見制度で判断能力が低下してから後見を開始する、という形態で契約を結んでいる場合、先にも少し触れましたが、本人の判断能力の程度を高頻度で確認できないような環境であると、判断能力の低下に気付くのが遅れてしまうという恐れがあります。
このようなときに活用したいのが、見守り契約です。支援者が高齢者と定期的にコミュニケーションを取るサービスで、日常において何か異変があったときにもすぐに気づくことができるというメリットがあります。
見守り契約を結んでおけば、任意後見制度への移行もスムーズに行えるでしょう。
財産管理委任契約
任意後見制度が判断能力低下「後」に利用できるのに対し、財産管理委任契約は判断能力低下「前」に利用できる制度です。
その名の通り財産管理をまかせられる契約であり、判断能力は十分ではあるけれども高齢を理由に財産の管理に不安がある、というときに結んでおくとよいでしょう。
この契約はいつでも開始が可能で、任意後見制度に移行していくことももちろんできるため、判断能力低下の前後でうまく使い分けられますが、任意後見監督人のように財産管理者を監視する立場の存在がない点に注意が必要です。
任意代理契約
こちらも判断能力低下「前」から利用できる制度であり、財産管理委任契約との併用がもっとも効果的なものです。
なぜかというと、財産管理委任契約では、文字通り「財産管理」しか委任することができないのですが、任意代理契約は「法的行為の代理」を委任できるからです。
お互いを補い合えるという関係性であるため、判断能力低下前にはこのふたつの制度の併用で、万全の準備ができることでしょう。
遺言書
もし任意後見人に財産を多く遺したい、などの希望があるなら、遺言書の作成もしておくのがよいでしょう。
遺言書がなければ、遺産分割協議を経て相続人全員の合意があれば協議の内容通りにしか相続が発生しません。そのため、判断能力が低下する前から任意後見人に何らかの遺産相続をさせたいのであれば、遺言書の作成がもっとも重要といえるのです。
まとめ
任意後見制度は、高齢者サポートのための制度ではありますが、できることとできないことがあります。まずは何ができるのかという特徴をしっかり把握したうえで、足りない部分やさらに希望するサポートがある場合は、ほかのさまざまなサポート制度と併用することで補えば、備えはさらに万全となるでしょう。
手続きの煩雑さなどが気になるのであれば、部分的に専門家の助けを借りることも検討するとよいですね。